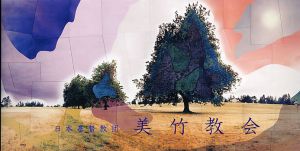「崩れ落ちる壁」ヨシュア6:12~21、Ⅱコリント5:18~19
2025年10月12日(左近深恵子)
人として生きることが許されなかったエジプトを、神さまがお立てになったモーセに率いられて後にしたイスラエルの民は、神さまから約束された地を目指して荒れ野を40年さすらいました。エジプトから荒れ野に出た第一世代は、約束の地を見ることなく旅の間に生涯の歩みを終え、民は新しい世代となりました。それは、第一世代の民が、約束の地の町が壁に囲まれて守りが堅いこと、その民は大きく強いことを偵察隊から聞くと怯み、自分たちをエジプトから連れ出したモーセを詰り、つまりは神さまに抗ったためであると、聖書は伝えます。アブラハム以来、神さまがご自分の民に約束されたカナンの地を前にして、モーセの生涯も終わりを迎え、モーセの後継者としてヨシュアがイスラエルの民を率いる者とされ、神さまはヨシュアにこう言われました、「さあ今、あなたとこの民は皆立ち上がり、このヨルダン川を渡りなさい。その先には、私がこの民、イスラエルの人々に与える地がある。・・・あなたがたの足の裏が踏む所をことごとくあなたがたに与える」。約束の地へと向かう民の行く手を、ヨルダン川が阻んでいます。急峻な谷を激しく流れるヨルダン川のほとりには、村落もありません。誰にとっても渡河が困難な激流ですが、神さまはヨシュアに、共におられ、見放すことも見捨てることもないと約束されます。そして、神さまの言葉に従ってイスラエルの祭司たちが、十戒が刻まれた石の板が納められている主の契約の箱を担ぎ、命を神さまに委ねて川の中へと足を踏み出すと、足の裏が水につかるやいなや上流で川の水がせき止められ、イスラエルの民は皆川底が露わになった川を渡り切ります。エジプトを発った時、葦の海の水を分けてファラオの軍勢から神さまが救ってくださった不思議なみ業のように、神さまはヨルダン川の中に道を通してくださいました。神さまに依り頼んで進んだ民は、約束の地の大地を足の裏で踏みしめることができました。
こうして渡った約束の地で最初に為されたのが、エリコという町を占領することでした。神さまはご自分の民にカナンの地を委ね、そこで神様の祝福の基とされると、民は栄え、神さまの祝福を他のあらゆる民にもたらす民となると約束されました。約束の地を委ねてくださる聖なる神さまにお応えしてその地を管理するということは、神さまではない神々の偶像を崇拝する民からその地を取り戻すことを伴います。その第一歩が、エリコの町の占領でありました。
イスラエルの民はヨルダン川を東側から西側へと渡ったのでしょう。西側の民の王たちは皆、イスラエルの人々のために主がヨルダン川の水をせき止めて渡らせたことを伝え聞いて心が挫け、イスラエルの人々に立ち向かう勇気を失ったと聖書は伝えます。エリコの町の人々もそうでした。古くから栄えたエリコの町の周りには古来石の壁が築かれ、紀元前8,000年紀には既に、高さ4メートル、厚さ2mもの城壁が築かれ、高さ8mを超える監視塔も備えられていたそうです。その後更に外側により高い城壁が築かれました。ヨシュアたちが目にしたのはその壁であったのでしょう。交通の要所でもあるエリコの城壁の門は、いつもで多くの人が行き来していたでしょうが、イスラエルの民の渡河を耳にすると城門は堅く閉ざされました。壁の中からは外の様子の監視が可能であるのに、外からは中の様子が全く分からない、何をしても崩すことなどできない規模の城壁に囲まれたこの町は、まさに難攻不落の要塞であったでしょう。イスラエルの民を導く神が示した力に心挫け、この民に立ち向かう勇気を失ったからと言って、エリコの王や民は町をイスラエルの民に明け渡して出て行こうとはしません。イスラエルの神の力にはかなわないが、この厚い壁の内側に籠り続ければやり過ごせると思ったのかもしれません。けれど主はこの時既にヨシュアに、「私はエリコとその王、その力ある勇士たちをあなたの手に渡す」と告げておられます。「私は渡した」、「私は今やあなたの手に渡す」との意味であります。ヨシュアたちには今、圧倒的なスケールの壁が侵入を阻むのが目に見える現実であっても、ヨシュアたちにこの町を委ねることを既に神さまは定められ、イスラエルの勝利は今やヨシュアの手に与えられていると告げられたのです。
既に神さまが差し出しておられるものを神の民が受け留めるため、神の民は何を為すべきなのか。神さまが告げられたことが6章の前半に記されています。神の民の戦士たちと7人の祭司が、主の箱と共に一日一度、町の周りを一巡りすること、戦士たちの後を行く祭司たちはそれぞれ雄羊の角笛を吹き鳴らし、主の箱の前を進み、これを6日の間続けること。そして7日目には町を7週すること。ヨシュアが命じた時に戦士たちは鬨の声を上げ、そうすると町の城壁は崩れ落ちるということでした。
この不思議な指示は、要塞のような町を前にした者が普通期待するであろう、町を攻略するための作戦には程遠いものです。軍事的作戦の指示を求めるなら、町の中から、壁の外を毎日巡る一団の様子を監視することが可能であり、角笛まで吹いているのに、6日の間沈黙を命じられるのは何のためなのか、兵糧攻めにする作戦としては6日間は短すぎる、神さまのお力によって最後に兵士たちの鬨の声と共に壁が崩れるならば、第一日目にそのお力を発揮してくださっても良いではないか、などと思うかもしれません。
主が示されたことは、祭司たちを中心に行われる祭儀と言えます。町を巡る一行の中心にあるのは主の箱、つまり神さまから与えられた契約の言葉です。神さまの言葉に仕える祭司たちが主の箱を担ぎ、その前後を戦士たちが守りつつ進みます。祭司たちの数については、その手にしている角笛の数まではっきりと7と指示されていますが、戦士たちについては数が記されていないこと、祭司たちの角笛の音だけが鳴り響き、他の者たちは沈黙を守っていることにも、この行列の中心に神さまの言葉があることが示されます。
祭司たちは角笛を手にしていましたが、神の民にとって角笛で思い起こされるのは、シナイの山で神さまがモーセに現れてくださった時、「三日後に全ての民の前で主がシナイ山の上に降られると、民は山に登ってはならない、雄羊の角笛が吹き鳴らされる時、民は山に登ることができると言われ」、三日後の朝、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上に臨み、角笛の音が極めて力強く鳴り響いたので、モーセは民を神さまに出会わせるために山の麓に導いた」とあります(出エジプト19章)。そのシナイの山でモーセを通して与えられたとされる律法には、主が与える地に民が入る時、その地は主の安息を得なければならないと7年毎の安息年が定められ、7度の安息年の後、贖いの日が到来すること、祭司たちはその訪れを民に告げ知らせるために角笛を吹き鳴らすことが定められています。7度の安息年の次の年、つまり50年目を聖別し、解放を宣言せよと、それはそれぞれが自分の土地、自分の氏族のもとに帰る年であるとも定められています(レビ記25章)。祭司たちがエリコの城壁の外を回って7日目に吹き鳴らした角笛の音は、神さまの約束の実現を阻む民の壁が崩され、神の民を約束の地に帰らせてくださる時の到来を告げるものであったのかもしれません。
かつて第一世代の人々は、カナンの地の町が壁で囲まれていることを聞くと、主の約束に従って進もうとのヨシュアやカレブの言葉に耳を傾けることができず、主の約束に信頼することができず、約束の地に入ることができませんでした。ヨシュアが率いる荒れ野で生まれ育った、堅固な城壁に囲まれた町を初めて見る新たな世代の民も、このような町に攻め入った経験も無ければ、攻め入るのに十分な装備もありません。第一世代がそうであったように、壁の堅牢さに怯む思いが沸き起こって当然であったでしょう。ただ神さまの言葉への信頼において、ヨシュアと一行はエリコの町の周りを巡る一歩を踏み出します。戦士たちは自分たちの経験と装備を頼りに戦いに向かうためではなく、神さまの言葉に従い、神さまに捧げるこの行進に加わるために踏み出します。祭司たちはこの神さまに捧げる行進を神さまの言葉に従って執り行うために、踏み出します。壁を崩すにはもっと現実的な行動をすべきではないか、神さまに捧げる無言の行進よりも、自分たちを鼓舞するようなことが必要なのではないか、そのような思いがおそらく彼らの内側からも外側からも彼らの足元を揺さぶったことでしょう。けれど彼らは、共におられ、約束を与えてくださる主に、自分たちの今を捧げ、自分たちの行動を捧げることを、一日、一日、続けたのです。
6日間この行進が続けられそして7日目、いよいよ7週回る日が来ます。大きな都を7周巡るためでしょう。夜明けとともに起きて行進を始めます。7週目に祭司たちが角笛を吹き鳴らした時、ヨシュアは兵に鬨の声を上げよと命じます。鬨の声が上がると城壁は崩れ落ち、兵はそれぞれの持ち場から町に突入し、町を占領しました。戦士たちはヨシュアが命じたように、町の中にある全てのものを滅ぼし尽くし、町の住民も剣に掛けました。ただ、先にエリコの町の中を探らせるためにヨシュアが送り込んだ二人の斥候を匿い、エリコの町の王が遣わした者たちから助けてくれたラハブとその家の全ての者は保護します。ラハブと家の者たちはその後イスラエルの民の中で暮らすようになったと、6章の終わり部分で伝えられています。
兵たちが町の中にあるすべてのものを滅ぼし尽くしたこと、その町の住民を剣に掛けたことに、私たちは大きな戸惑いを抱かずにはいられないのではないでしょうか。滅ぼし尽くすことはここではヨシュアが民に命じていますが、遡ると申命記で主がモーを通して命じられたことです。この要求は、理解が非常に難しいものでありますが、イスラエルが様々な民が既に統治を誇っていたカナンの地に移り住み、周辺の敵対する民の只中で生き残ってゆくために、必死に闘う他なかった時代に見られる教えと考えられています。実際の歴史的経過はかなりの期間に及ぶ波状的なものであって、軍事的な闘いもあったかもしれませんが、他の民があまり居ない山地を中心に平和的経過をたどって定着した面も、町の支配者に抗ってそこから出たカナンの地の者たちがイスラエルの民に加わった面もあるのではないかとも言われています。いずれにしても、先週も触れましたように、ヨシュア記はカナンの地を取得してゆく出来事を歴史的に記録した文書ではなく、歴史の中を歩んだ神の民と共に神さまがおられたことを伝えるものであります。
聖書は主なる神が、イスラエルが闘いで獲得したものは、捕虜であれ戦利品であれ、剣にかけるか、完全に破壊し焼き付くすことで、主に捧げなければならないと、主に捧げ尽くすことを求められたことを伝えています。そうすることによって、戦いの真の勝利者はイスラエルではなく、その地の民が礼拝する偶像の神々ではなく、主なる神であることを、この地を、この町を統治されるのは神さまであることを、証しするためでありましょう。ヨシュアは主のご意志に従って、民に命じたのでしょう。町の周りを巡ることが、軍事的な作戦ではなく、祭儀として為されたように、滅ぼし尽くす行為も軍事的な戦闘としてではなく、霊的な戦いとして伝えられています。だから、滅ぼし尽くすべきものが何であろうと、自分の所有にしてはならないことも命じられています。焼き尽くすことのできない金属は、主への聖なる献げものとして主の宝物庫に納めることも、命じられています。価値のあるものだからと自分の所有にするのは、この勝利がただ神さまのものであることを否定することになります。十戒で「私をおいてほかに神々があってはならない」(出エジプト20:3)と、言い換えるなら「あなたには、私をおいて他に神々があることはあり得ない」と断言された、ただお一人の神さまを礼拝し続け、神さまの祝福の基となるため、神の民はエリコの町で戦ったのです。
エリコに続いて、他の町でも滅ぼし尽くすことが命じられますが、実際に全てのものを滅ぼし尽くすことはできなかったことも、ヨシュア記に記されています。エリコの町で、心を開き、イスラエルの神を受け入れ、斥候二人を匿ったラハブとその家の者たちは滅ぼさず、保護しています。徹底して「滅ぼし尽くす」ことが求められるのは、偶像崇拝を徹底的に退け、この町を神さまに献げるため、神の民としてのアイデンティティを失わないためではないでしょうか。戦利品によって暮らしを豊かにするためではなく、敵意によって相手を抹殺するためでもなく、神さまではないものを神としてしまう悪を滅ぼし尽くすためではないでしょうか。
けれど人間は、悪を滅ぼし尽くし、神さまの聖さにふさわしい状態にし続けられない弱さを抱え続けます。この先神の民イスラエルの王とその民自身が、神さまではないものに依り頼む悪に陥ってゆきます。イスラエル自身も滅ぼし尽くされなければならない者となり、神さまから委ねられた約束の地を汚してゆきます。主がこのことを全ての者に徹底的に求めたら神さまの裁きによって滅ぼされずに済む者は誰もいません。罪の統治から神さまの統治の中へと導き入れるために、神さまは私たちが受けるべき裁きをみ子にくだされて、罪深い私たちを生かしてくださいました。み子はその命をささげて、私たちには切り拓くことのできない道を、神さまに至る道を切り開いてくださった、私たちには崩すことのできない神さまとの間の壁、他者との間の壁を、ご自身の命の値によって崩してくださった、その私たちにも、神さまをおいて他に神々があることはあり得ないのに、真の神を神としきれない罪を抱えるものであることに、気付かされるのです。
コリントの信徒たちへの第二の手紙でパウロが記した言葉を先ほど聞きました。「神はキリストにあって世をご自分と和解させてくださった」と2度も繰り返し、私たちは既にキリストの十字架と復活によって神との間に和解がもたらされた者であることを語ります。「人々に罪の責任を問うことなく」、私たちに罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねてくださっています。この恵みはすべて神さまから出ています。神さまから委ねられた和解の務めを担う一歩を、神さまから授けられた和解の言葉に生きる一歩を、ただ神さまに依り頼んで踏み出してゆきたいと願います。