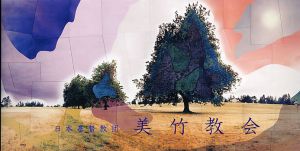「強く、雄々しくあれ」ヨシュア1:1~9、Ⅱコリ4:7~10
2025年10月5日(左近深恵子)
「強く、雄々しくあれ」というフレーズが、今日の箇所の中で3回も繰り返されます。聖書の中でもよく知られたフレーズの一つです。このフレーズに力づけられたことがある方は多いのではないかと思います。
このフレーズは今日の箇所では主がヨシュアに対して言われています。そしてこの先1:18ではイスラエルの民がヨシュアに、主のこの言葉を繰り返すように、「あなたはただ、強く、雄々しくあってください」と言います。更に10章ではヨシュアが民に「強く、雄々しくあれ」と言っています。主の言葉をもって、ヨシュアと民は互いに語り掛けています。
このフレーズは、ヨシュア記の今日の箇所で初めて登場するのではありません。申命記の終わりの部分で、モーセがこの言葉を先ず民に告げ、次にヨシュアに告げ、最後に主がヨシュアに告げておられます。ヨシュア記は、申命記を受けるようにして、綴られている文書です。「強く、雄々しくあれ」という呼びかけをもって主から語り掛けられ、互いにこの言葉によって呼び掛け合う関りも、申命記を引き継いでいるのです。
ヨシュア記が申命記を引き継いでいることは、申命記がモーセの死について記し手終わり、ヨシュア記が「主の僕モーセの死後、主はモーセの従者であったヌンの子ヨシュアに言われた」との文で始まっていることにも示されています。
モーセについて、この所礼拝において出エジプト記を通して聞いてきました。モーセは、古代イスラエルの民をエジプトから導き出すために神さまが選び立てられた人物です。出エジプトの出来事は、人として生きることが許されなかった奴隷の地からの救出であり、また、神さまの約束の地に再び戻るための出発でありました。古代イスラエルの民はかつて神さまから、カナンの地にあって大いなる民となり、神さまの祝福をあらゆる民にもたらす祝福の源とされるとの約束を与えられました。アブラハム、イサク、ヤコブを通して約束を与えられました。ヤコブの時代に、飢饉がその地域一帯を襲い、飢饉の中でも食糧が豊富なエジプトへと移り住むことになった時、約束の地を離れることを恐れたヤコブに神さまは、エジプトでも共におられると、必ずこの地に再び導き上ると告げてくださったので、ヤコブは安心して一族を引き連れてエジプトに移住することができました。しかし時代が進み、ヤコブ一族から大きくなったイスラエルの民がエジプトで暮らしている、その経緯を知ろうとしないファラオは、イスラエルの民から自由を奪い、虐殺や過酷な労働によって人数も力も抑え込もうとしてきました。助けを求めた民の叫びに耳を傾けられた神さまは、民を救い出し、約束の実現へと大きくみ業を推し進められたのです。この時エジプトを出発したのは、イスラエル民族に、イスラエルの神に従う道を選び取った人々も加わった、種々雑多な人々から成る群れでした。約束の地カナンを目指して進む民を、神さまの導きと守りの内にモーセが先導しました。その旅は40年に及んだと聖書は伝えています。そして約束の地を前に、モーセの生涯は閉じられます。エジプトで奴隷であった第一世代の民の大半も、その土地に入る前に死の時を迎えます。その背景には、民数記が伝える出来事があります。かつて、約束の地の傍まで辿り着いた民に、神さまはその地がどのような所であるのか探るため、偵察隊を遣わすことを命じました。各部族から偵察隊が選ばれ、その中にカレブとヨシュアもいました。偵察から戻った人々は、カナンの地の豊かさだけでなく、そこに住む民は強く、町は城壁に囲まれていると全会衆に告げ、その地に入ることは困難だと人々に思わせました。カレブとヨシュアだけは、進むべきだと、私たちには必ずできると主張しましたが、人々は主に信頼する二人の言葉にではなく、困難さを主張する者たちの言葉に耳を傾けます。なぜこのような所に自分たちを連れて来たのだと、エジプトで死んでいた方が、あるいは荒れ野で死んでいたほうが良かったとモーセを非難し、主に抗いました。主はご自分の約束に信頼しない民に対し、「私の栄光と、私がエジプトと荒れ野で行ったしるしを見ながら・・・私の声に聞き従わなかった者は誰一人として、私が彼らの先祖に誓った地を見ることはない」と告げられました。こうして第一世代の中でヨシュアとカレブだけが生き残り、主なる神はモーセの死後の、モーセが担って来た務めを引き継ぐ者として、ヨシュアを立てられたのです。
申命記の終わりには、約束の地を前にして、モーセがイスラエルの全ての人に、後継者がヨシュアであることを告げる場面が記されています。そこで先程触れましたように、「強く、雄々しくあれ」というフレーズが繰り返されます。神さまから与えられた約束に信頼して、カナンの地に入るということは、その地を支配している人々を追い払うことを伴います。かつて前の世代がその地の民を恐れ、上手くゆかないことを恐れ、前へと進むことを拒み、モーセに不満と怒りをぶつけ、神さまに抗ったことを思い返しながら、モーセは民にこう告げたのではないでしょうか。「あなたの神、主があなたに先立って渡り、あなたの目からこれらの国民を滅ぼされる。それであなたは彼らを追い払うことができる。主が告げられた通り、ヨシュアがあなたの先を渡って行く。・・・主は彼らをあなたがたに引き渡される。あなたがたは、私が命じたすべての命令の通りに彼らに行わなければならない。強く、雄々しくあれ。彼らを恐れ、おののいてはならない。あなたの神、主があなたと共に進まれる。主はあなたを置き去りにすることも、見捨てることもない」。それからモーセは民の見ている前でヨシュアを傍に呼び、今度はヨシュアにこう言います、「強く、雄々しくあれ。主が先祖に与えると誓われた地に、この民を導き入れるのはあなたである。あなたはそれを彼らに受け継がせなさい。主ご自身があなたに先立って行き、あなたと共におられる。主はあなたを置き去りにすることも、見捨てることもない。恐れてはならない。おののいてはならない」(申命記31章)。ヨシュアも、再び約束の地を前にしながらかつてのことを思い出していたのではないでしょうか。神の民と言えども人は、この先降りかかるかもしれない困難を恐れる時には、これまで主が示してこられたことも、主からいただいてきた恵みも忘れてしまい、自分たちの指導者を激しく詰り、雪崩を打つように主に背く流れに呑み込まれてしまう弱さを抱えている者であることを。そしてこの世代は、エジプトでの奴隷の苦しみをその身で味わい、そこから逃れるために、旅を続けてきたわけではないのです。荒れ野で生れ、荒れ野しか知らないこの世代が、カナンの地に愛着や郷愁を持っているはずもありません。この民を率いるヨシュアが、恐れ、おののくのは当然でありましょう。民が前へと進むことができるのは、苦しみからの逃避のためでも、この先の土地への郷愁や愛着のためでもなく、ただ神さまの約束への信頼に拠ります。神さまへの信頼が無ければ、一歩も前へと進めません。民にも、ヨシュアにも、「強く、雄々しくあれ」との呼びかけが必要であるのです。
申命記を受けてヨシュア記は、約束の地にイスラエルの民がはいってゆくことから始まります。ヨシュア記以降、士師記、サムエル記、列王記がイスラエルの歴史を綴り、列王記の終わりにおいてイスラエルの民は、捕囚とされます。ヨシュア記から列王記に至るイスラエルの歩みは、エルサレムの神殿も都も滅ぼされ、約束の地での生活が奪われ、民が分断され、主だった人々が異国の地に強制連行された時代から、約束の地に導き入れられた時代を見つめながら、記されたと考えられています。神さまによって、奴隷の地から導き出され、約束の地へと導き入れられ、その地を委ねられたのに、やがて神さまではないものに仕えるようになってしまったイスラエルの王たちと、それに追従してしまったイスラエルの歩み、神さまによって自由を回復され、自由の内に神さまに従う道を律法によって示されているのに、律法に示されている神さまのみ心を重んじず、神さまに従わなかったイスラエルの歩みが、その地を失った捕囚の出来事から見つめられています。捕囚は、神さまではない者を神とするイスラエルの長い歩みに対する神さまの裁きなのだと見るところから、ヨシュア記以降の歴史が綴られていると考えられています。従ってヨシュア記は、カナンの地取得の出来事を歴史的に記録した文書ではなく、歴史の中を歩んだこの民と共におられる神さまを伝えるものです。様々な神々を崇める諸国民の中で生きてゆく神の民の歩みの中で、歴史を超えて貫かれた神さまの救いのみ業を伝えるものです。神の民はその土地へと進み行くように神さまから命じられますが、それは土地を所有するためではありません。神さまからその土地の管理を委ねられた者として、入るのです。土地はイスラエルの王や民のものではなく、神さまから託されるものです。与えると約束された神さまは、その地を管理する責任を果たさない民から取り上げることもおできになる方です。神さまから土地を委ねられ、その土地の、様々な神々に従う人々と対峙してゆくヨシュアに、神さまは、共におられ、約束を実現されることを告げます。神さまへの信頼に立つようにと、「強く、雄々しくあれ」「あなたはただ、大いに強く、雄々しくありなさい」と告げておられるのです。
かつて、アブラハムは、「信仰によって・・・自分が受け継ぐことになる土地に出て行くように召されたとき、これに従い、行く先を知らずに出て行きました」(ヘブライ11:8)。多くの真の預言者たちが、ただ神さまの器となることを求めて、危機の中でも神さまの言葉に従い続けました。詩編の詩人も「涙と共に種を蒔く人は/喜びの歌と共に刈り入れる。種の袋を背負い、泣きながら出て行く人も/穂の束を背負い、喜びの歌と共に帰って来る」(126:5~6)と歌いました。神さまに信頼する者の強さを聖書は証しています。その強さとは、私たちのイメージを善い意味で壊し、私たちを励ます、強さです。
「強く、雄々しくあれ」、このフレーズに私も力づけられてきました。二つ目の「雄々しく」という日本語の言葉のイメージに距離を感じることもありましたが、この言葉は最初の「強く」という言葉同様、強くあることを指しています。英語の聖書では、この二つ目の言葉は、勇気を持つことを意味する「courage」が訳語に用いられ、このフレーズは「be strong and courage」と訳されてきました。同じように「勇気」や「勇敢」を意味する英語に「brave」という言葉があります。「brave」は、行動そのものが勇敢であることや、もともとその人が持っている行動力を指します。何事も恐れることの無い勇敢な戦士の勇ましさを表すイメージがある言葉であり、遡ると「野蛮さ」「凶暴さ」も意味する言葉です。英語の翻訳において、その「brave」ではなく、勇気を持って困難に立ち向かう内面的な力、恐れを感じながらも行動する力を意味する「courage」が用いられてきたことに、教えられる思いがします。「雄々しくあれ」「勇気をもって立ち向かえ」、そう訳されてきたこの言葉は、励ましの言葉です。前の言葉と併せて、「動ぜずしっかりしていなさい」と呼び掛けます。何によって、何のために動じないのかが大切です。神の民にとって他の民との闘いはこれまでもあり、この先も起こります。ヨシュア記はイスラエルの民が闘いによって他の民を追い払ったことを記していますが、実際はもっと緩やかな入植であったと、戦いの描写は寧ろずっと後の時代の歴史を反映しているとも言われます。いずれにしても、神さまが求めておられるのは戦いそのものではなく、神さまの祝福の基としてイスラエルの民がこの地で栄えることであるのでしょう。
約束の地を前に、主がヨシュアに告げておられるのは、「立ち上がり」、約束の地の前を流れる「ヨルダン川を渡りなさい」と言うこと、そして「律法をすべて守り行い、そこから右にも左にもそれてはならない」ということです。「あなたの力を駆使して、勇猛果敢に敵を倒し、土地を獲得せよ」とここで言われているのではありません。川を渡ってその地へと踏み入れ、一足、一足、律法に従って進むことを、神さまが与えてくださった生き方の道標である律法に従い、神さまのみ心に従って歩みを進めてゆくことを、ただ求めておられます。その歩みに結果をもたらしてくださるのは神さまです。既に神さまから与えられている約束と、既に受けてきた恵みを、一足、一足進む度に新たに確認し、新たに受け止める、そのような歩みを始めるために、あなたと民は立ち上がり、川を渡りなさいと言われています。
先ほど、パウロがコリントの教会に記した文書から聞きました。パウロの福音を宣べ伝える働きに対し、不当な評価や甚だしい誤解、中傷が浴びせられてきました。アジア州では、パウロは耐えられないほどひどく圧迫されて、自分たちは生きる望みさえ失い、死の宣告を受けた思いまでしたと、だからこそ、そのことによって、自分を頼りにすることなく、キリストを復活させられた神さまを頼りにするようになったのだと、これほど大きな死の危険から私たちを救ってくださり、この先も救ってくださるに違いないと、ただ神さまに望みを置いていると、この手紙の始まりにおいてパウロは記しています。今日の箇所でも、「四方から苦難を受けても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、迫害されても見捨てられず、倒されても滅びない」と言います。苦難を受けなくなると言うのではない、途方に暮れることが無いとも、迫害されることは無いとも、倒されないとも言いません。困難に会うことは避けられないが、その中でもがいていても、行き詰まらない、失望しない、自分たちは見捨てられないから、滅ぼされないから、そう言います。自分たちは欠けだらけのもろい土の器である。芸術品のような特別な価値はない、本来の器としての機能を持つだけのものであるけれど、その中に福音を委ねられ、福音を納め続けているのだと。倒されても、苦難を受けても、途方に暮れても、迫害されても、決定的に敗北しない、この測り知れない力は神さまからのものであると、復活のキリストの命がこの身にも現れるのだと、喜んでいます。土の器であることを認め、受け止め、み子の復活によって、恐れに呑み込まれずに進んでゆくパウロは、約束の地を自分の足の裏で一足、一足、踏みしめて進む者であったのです。
私たちは独りではありません。私たちをお造りくださった神さまに背き、あちこちに欠けを生じさせ、ひび入らせ、歪みを生じさせてしまう私たちのために命を捨ててくださって、復活の初穂となられたキリストが共におられます。納めている神さまからの福音、神さまからの祝福を、証ししながら、先立って行かれ、共におられる主への信頼において一歩一歩、力強く、動じることなく、歩んでゆきたいと願います。