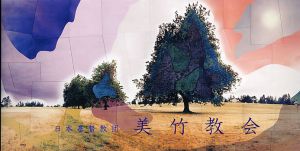「雲の柱、火の柱」出エジプト13:17~22、使徒18:5~11
2025年9月21日(左近深恵子)
イスラエルの民を去らせよとの神さまの言葉を拒み続けるファラオと、神さまが遣わされたモーセとアロンの間に、息詰まるような対決が続けられてきました。ファラオが拒む度に神さまは災いをファラオとエジプトの民にもたらされました。最後の災いは、過ぎ越しの出来事と呼ばれる決定的なものでした。エジプト中の初子が、ファラオの初子も例外なく打たれ、死んだ中、神さまの言葉に信頼し、犠牲の小羊の血を家の入口に塗っていたイスラエルの家は過ぎ越され、無事でした。王座を継ぐ筈だった我が子も失ってファラオはようやく、モーセとアロンに「私の民の中から出て行きなさい」と急いで出て行くように命じました。エジプト人もイスラエルの民をせきたてて、急いでその地から去らせようとしました。そこでイスラエルの民は、エジプトの地を後にしたのでした。
10もの災いをもたらすことなどせずとも、神さまがそうお決めになれば、イスラエルの民をエジプトからそのお力をもって救い出すことがおできになったことでしょう。しかしそれではファラオもエジプトの民も、一過性のアクシデントに見舞われたように思って終わりだったのではないでしょうか。イスラエルの民がエジプトを出る理由は、自分たちの神、主にいけにえを献げるためだと、そうファラオに言うようにと、神さまはホレブの山でモーセにはっきりと告げておられます。奴隷として過酷な労働を課せられている苦しさや、人として扱われない辛さが勿論あります。その根底にあるのは、自分たちの神さまを神とし、神さまを礼拝し、神さまに従う自由が奪われていることにあります。ファラオが自分以外の者を主とすることを許さないことにあります。そのファラオとファラオの支配に追従しているエジプトの人々の上に神さまが「手を伸ばし、イスラエルの人々を彼らの中から導き出したとき、エジプト人は私が主であることを知るようになる」と神さまは言われています(出7:5)。過越しの出来事に至るまで重ねられた激しいやり取りは、イスラエルの民が信じる神さまこそが全てを支配しておられる主であることを、ファラオとファラオの民に、神さまが忍耐強く知らしめるものであったのです。
このやり取りの間イスラエルの民は、神さまがファラオやエジプトの人々に知らしめようとしていることを既に知っている者として、対決の背後で見守っていたことでしょう。自分たちの人生の日々も尊厳も踏み台にして繁栄してきた者たちが、今こそよく知るべきだと考えていたことでしょう。神さまもこの間、イスラエルの民に直接問うことはしてこられませんでした。エジプトを後にし、自由が回復された今、真の主を自らも主とする歩みがイスラエルの一人一人に問われることになります。
そもそも、イスラエルというエジプト人でないこの民がまとまってエジプトで暮らすようになった始まりには、神さまからイスラエルという名前を与えられたヤコブの、家族の中での争いがありました。アブラハムの孫、イサクの息子であるヤコブが、叔父ラバンのもとから故郷カナンの地に戻る時、兄エサウに殺されるのではないかと死の不安に襲われていました。そのヤコブに神さまが現れてくださり、一晩中格闘してくださり、夜が明ける頃、「神と闘い、人々と闘って勝ったから」との意味を告げて、イスラエルという名前をヤコブに与えられました。神さまがそうお決めになれば、すぐさまヤコブを打ち負かし、その罪に対して滅びと言う裁きを下すことができる方であるのに、祝福を求めてくらいついてくるヤコブの闘いを夜を徹して受け留め続けてくださり、滅びを超える祝福と新しい名前を与えてくださいました。ヤコブが「勝った」と言っておられますが、格闘の時を支配しておられたのも、ヤコブに祝福と新しい名前を与えられたのも、神さまでありました。イスラエルという名前には、「神が闘われる、神が支配される」という意味もあるそうです。自分の力と才覚に頼って欲しいものを他者から獲得し、多くのものを支配しながら、その生き方によって壊してしまった他者との関係に苦しむヤコブに、神さまは「神こそが闘われる、神こそが支配される」という名前の下で生きる新しい人生を与えられました。ヤコブは、自分の力や世の力が自分の人生を支配するのではなく、祝福を与えるために闘ってくださる神さまが人生を支配しておられることを知る者となりました。ここに、後にイスラエルと呼ばれるようになる神の民の在り方の核もあります。イスラエルの民とは、真の支配者は神さまであると知り、共におられる神さまとの結びつきにこそ祝福と幸いを見出し、神さまが信仰の父祖たちに与えられた契約に従って、この祝福を他の人々にももたらすことを願う群れであるはずです。
しかし、ヤコブの、妻たちとそれぞれの子どもたちとの偏った関係性は、息子たち同士の対立という結果を生み出し、互いに相手を支配しようと対立を深めた兄弟の争いは深刻なものとなり、兄たちは弟ヨセフをエジプトに行く隊商に売り飛ばしました。エジプトで奴隷となったヨセフでしたが、そこからファラオに次ぐ地位にまで上り詰めました。宰相ヨセフの先を見通した政策によって、飢饉がその地域一帯を覆った時、エジプトのみならず周辺の民も、エジプトから穀物を買って生き延びることができました。エジプトも更に国力を増しました。カナンの地で暮らしていたヤコブの家族もエジプトから穀物を得ることができ、その上ヨセフがファラオに掛け合い、一族は豊かなエジプトの地に移住することができました。イスラエルという名前を与えられた者の家族内の深い対立が、ヨセフをエジプトへと追いやりましたが、それによってイスラエルの家族は飢饉の中で生き延びることができました。豊かなエジプトに移り住めることに感謝しつつも、神さまからの約束の地を離れることに不安を覚えていたヤコブに、神さまはこの先もヤコブと共におられ、エジプトでも大いなる民とされると告げられ、ヤコブは安心してエジプトに向かいました。やがてヤコブの生涯が閉じられる時、ヤコブは自分をカナンの地の一族の墓に葬ることをヨセフと他の息子たちに約束させ、ヨセフは兄弟たちと共にヤコブを葬りました。ヨセフも死の時が近いことを知った時、自分の兄弟たちに、神さまは必ずこの地から約束の地に導き上ってくださると確信を告げ、その時には自分の骨をここから携え上るようにと頼みました。生涯の大半をエジプトで生き、エジプト全土を指導する立場にまでなり、エジプトで死の時を迎えても、自分のアイデンティティはイスラエルの子であることをヨセフは明らかにしています。今日の箇所でモーセはヨセフの言葉に従い、ヨセフの骨を携えています。それは、モーセとイスラエルの民が、ヨセフの骨と共にヨセフの信仰を大切に受け継いでゆくことの証です。信仰の父祖たちとの契約を神さまが実現してくださることに信頼し、踏み出すイスラエルの民の旅です。このイスラエルとは、ヤコブの血筋を受け継ぐ者だけではありません。エジプトを出発した人々の中には雑多な人々が多数加わっていたことが記されています(出12:37)。アブラハム、イサク、ヤコブの、神さまの契約に信頼する歩みを、世代を超えて大切にしてきた民と、その民のように神さまに信頼し、自分たちも自分たちのこの先を神さまにお委ねすることを決断した多くの雑多な人々から成る群れが、エジプトを後にしたイスラエルの民であるのです。
今日の箇所は、イスラエルの民がどのような旅へと踏み出したのか伝えます。神さまは、民を通常の近道のコースではなく、回り道のコースへと導かれたことが先ず告げられます。ペリシテ街道と呼ばれる地中海沿岸の道を進路としなかったのは、イスラエルの民がそう求めたからではありません。民が選んでいたら、早く目的地に着ける通常の道を選んだのではないでしょうか。神さまが回り道を取られました。ペリシテ人との闘いを神さまが恐れたからではなく、戦いを目前にした民が、エジプトを出て来たことを後悔し、エジプトへと戻ろうとすることを案じられたからです。奴隷の地から導き出されながらこの民は、現実に具体的な危機が身に降りかかりそうになると、神さまに従う道を求め続けられなくなると知っておられます。イスラエルの民だけではありません。人には、社会的に、政治的に、優勢な勢力に従おうとするところがあります。危機に揺さぶられると恐怖や怒りの感情に支配され、誰かに責任転嫁したり、過去を過大評価してしまうところがあります。ましてイスラエルの民はこれまでファラオの奴隷でした。ファラオから、ファラオ以外のものに仕えることを禁じられ、為すべき労働を命じられてきました。過酷な重労働であろうと、虐待であろうと、ファラオが命じることは何であろうと正しいのがエジプトの社会でした。そのファラオに従っているならば、奴隷であっても選ぶことができなくても衣食住を得ることができました。それ以外の生活を知らない元奴隷たちが、ファラオの支配の外に踏み出し、自由を与えられました。自由であるということは、正しいことが何であるのか神さまに問いながら自分で考えることが必要でもあるということでした。これまで与えられてきた寝る所、食べる物についても、この先求め続けなければならないということでした。見えない神さまのみ心を問いながら考え続けることよりも、目に見える人間から具体的に命令を出される方が楽だという思いを断ち切るのは、奴隷であった彼らにとって決して容易いことでは無いはずです。自由であるよりも、指示に従い、責任を誰かに転嫁していたい誘惑は、何度でもそこに引き戻されてしまうほど強い魅力を持っています。危機に直面する時ほど、人を惹きつけます。しかしその安心感は真の安らぎではなく、そこに引きずられることはその人にとって人として生きることのできない状態に陥ることを、人々はまだ十分知りません。出エジプトは、ファラオやエジプトを後にするだけでなく、この偽りの安心感と決別し、先が見えなくても神さまに信頼する歩みへと踏み出すことです。闘いという危機に直ぐに直面してしまう道を避けることで、滅びに至る道との決別を人々が受け入れられるように、神さまが民に備える時を与えてくださったのです。人の目には遠回りの、間違った道に見えても、神さまは人々にとって最善の道へと導いてくださったのです。
イスラエルの民がどのような旅へと踏み出したのか伝えるこの箇所は、神さまの導きによって全体が囲われています。最初に、神さまが近道ではない道へと導かれたことが述べられました。続いてヨセフの骨を携え行くことが語られ、結びにおいて神さまが雲の柱、火の柱で導かれたことが語られます。目に見える世の力に隷属する道と決別し、自由の内に主に従う旅は、先立って行かれる神さまに導かれる旅であることを、回り道と、雲と火の柱によって、知るのです。
雲の柱は、昼間の強烈な日差しから民を守りつつ、道を示すものでしょう。遮るもののほとんどない荒れ野で、日影がどんなに助けとなるか、長い、長い夏を超えて来た私たちには、これまで以上に神さまの慈しみを覚えずにはいられない雲のイメージではないでしょうか。
火の柱は、夜間、灯りなど無い荒れ野で、人々を力強く照らしたことでしょう。ペリシテ街道は避けたものの、他の民からの攻撃を受けないとは限らない旅路ですので、日中民は隊列を整えて進みます。けれど、民の中には女性も子どもも居たことが出エジプト記に記されています。年老いた者も、身体に重荷を負っている者もいたでしょう。雑多な民でもあります。夜の間は、闇に紛れて潜んでいる様々な敵に対して、一層脆弱な民であります。その民を闇に呑み込まれることも、強風にかき消されることも無い神さまの炎が、照らし、守ってくださったのです。
雲も火も、聖書において神さまの臨在を示すものとして登場します。モーセに神さまが語り掛けてくださったのは、炎の中からでした。この先シナイの山に神さまが降られた時には、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上に臨みます。昼と夜と、異なって見えるけれど、昼も夜も神さまの臨在をいつも知ることのできる柱が人々を導きます。昼の間はみ手の内に包まれているような神さまの雲に導かれて約束の地に向かって進み、夜になると炎の柱に守られて安心して荒野の大地に横たわり、眠りについたことでしょう。このような一歩一歩、一夜一夜を重ねて行く中で、それまではファラオに奴隷として従うことしかできなかった人々が、人として生きることのできる歩み、イスラエルの民としての歩みを、徐々に回復していったことでしょう。
使徒言行録18章には、コリントの地で道を模索するパウロの様子が伝えられています。ギリシアのアカイア州の州都として、商業や交通の中心地として大いに栄えていたコリントは、道徳的な乱れも広がり、悪徳と虚栄の町としても有名でした。この大都市でパウロはメシアはイエスであると力強く福音を語りましたがほとんど受け入れられず、失意の中にありました。ギリシアの文化に現れている人間の持つ力の素晴らしさに強い誇りをもっていたコリントの人々は、人間としての貧しさや不完全さを語るパウロの言葉に激しく抵抗し、口ぎたなく罵ります。会堂長のクリスポをはじめ、主イエスを救い主として受け入れ、洗礼を受ける人々も多数与えられ、教会が生まれましたが、大半の人々から福音が拒まれる状況に、パウロは恐れと孤独を覚え続けていました。そのパウロに神さまが「恐れるな。語り続けよ。黙っているな。私はあなたと共にいる。だから、あなたを襲って危害を加える者はない。この町には、私の民が大勢いるからだ」と語り掛けてくださいました。使徒パウロは、神さまが共におられること、それゆえ恐れる必要が無いことを、よく知っていたつもりであったでしょう。人々にもそう語って来たことでしょう。それでも自分の言葉は虚しく地に落ち、拒絶と敵意ばかり生んでいるのではないかという恐れ、自分の意思や能力の不十分さが福音を宣べ伝える働きを不可能にしているという恐れが繰り返し内側に沸き起こり、パウロの心を浸食してきたことでしょう。「恐れるな。語り続けよ、黙っているな。私はあなたと共にいる」と語り掛けられ、神さまの臨在を新たに受け止め、神さまに背中を押されるように再び語り始める中で、伝道は自分の力に拠るのではなく、共におられる神さまの導きによるのだと気づかされ、この町に大勢いるご自分の民を探し求めておられる神さまのみ業に、自分は招き入れられているのだと、福音を宣べ伝える喜びを新たにされたことでしょう。そうして、人の目には伝道が極めて困難に思えるこのコリントの地にパウロは1年半もの間腰を据えて伝道を続け、コリントの教会は大きく成長しました。この時期にパウロの重要な書簡が幾つも記され、初代教会の基盤が築かれたと言われています。
神さまが共におられること、先立ち導いてくださることを、み言葉と聖霊のお働きによって新たに気づかされ、み言葉に従い、福音を他の人々と分かち合う歩みを続けることを通して、現代のイスラエルの民としての教会の歩み、私たち信仰者の歩みは導かれてゆきます。人の目には厳しい状況であっても、それこそが神さまの導きによる最善の回り道かもしれません。神さまこそが闘われる、神さまこそが支配される、この確信と喜びと驚きは、神さまに従う歩みを続ける者にもたらされるのです。