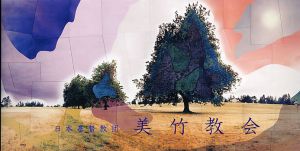「主は叫ぶ声を聴いた」出エジプト3:1~10、使徒7:30~35
2025年9月14日(左近深恵子)
モーセはエジプトで、イスラエルの民の一人として生まれました。イスラエルの民が過酷な環境に置かれていた時代でした。なぜイスラエルの人々がエジプトで暮らしているのか、どれだけエジプトに貢献してきたのか、その歴史を知らない新しいファラオが、イスラエルの民の人口が増加することに恐怖を覚え、敵意を抱き、イスラエルの民に苛烈な労働を課し、それでも人口が減らないからと、イスラエルの民の家に生まれた男児は皆殺すようにと命じていました。モーセが生まれた時、何とかこの子の命を守ろうと知恵と力を尽くした母親と姉、そしてモーセをイスラエルの男児と知りながら殺させまいとしたファラオの娘によって、モーセは少なくとも離乳までは実の母親のもとで母親に育てられ、その後はファラオの娘に引き取られ、モーセと名付けられ、エジプト王女の息子として王宮で育ちました。ファラオはエジプト人とイスラエルの民に、敵意と恐怖心で隔てられた関係をあてがおうとしましたが、三人の女性たちはそのような隔てを超え、エジプト人とイスラエル人というボーダーを超えて、神さまから与えられた一人の子の命と成長に必要なものを守りました。こうしてモーセは、虐待され、虐殺される側の民出身でありながら、その民を虐待し虐殺する側の、それも王族という、安全が確保され、何不自由ない境遇で成長しました。エジプトの教育を受けたモーセは、エジプト人と同化することを求められたことでしょう。その求めに抗わず、自分の出自を忘れてしまえば、安全と裕福な暮らしだけでなく、自分のアイデンティティと向き合うことも無く生きてゆくことができたでしょう。しかし成人したモーセは、ファラオの圧政に喘いでいるイスラエルの人々こそが自分の同胞と考えるこころを持ち続ける人となっていました。王宮に居ても同胞の民を思わずにはいられないモーセはある日、イスラエルの民の所へと出かけて行きます。同胞が強いられている苦役の実態を見ようと出かけたのでしょう。しかし想定していた状況よりも悲惨な現実だったのではないでしょうか。労働を監督していた1人のエジプト人が、同胞を虐待している現場を目撃したモーセは、同胞を助けるためだと、密かにそのエジプト人を殺してしまいました。
翌日もモーセは同胞の民のところへ出かけて行きます。今度は同胞が仲間同士で争っているのを見て、仲裁に入り、一方をたしなめると、その相手から「誰がお前を我々の監督や裁き人としたのか。あのエジプト人を殺したように、私を殺そうと言うのか」と言われてしまいます。予想だにしていなかった言葉でありましょう。昨日したことが既に同胞たちに知られていたことも、同胞たちの反応が期待していたものと全く違っていたことも、モーセには驚きであり恐怖でありました。モーセはイスラエルの民を同胞だと思ってきました。しかしイスラエルの民の方は、虐待する側の王族として生きて来たモーセのことを同胞とは思っておらず、それどころか反感を持たれていました。モーセが正義だと取った行動は彼らには正義ではなく、自分は暴力でエジプト人を殺しながら、自分たちに暴力を振るうなとたしなめるのかと、自分たちより高みから裁こうとしている、自分たちを支配しようとしていると、モーセの介入を拒んだのでした。
更に、モーセがエジプト人を殺害したことがファラオにまで知られ、ファラオはモーセを死刑に処するために追っ手を遣わします。ファラオは、娘の願いを聞き入れ王族の一人として生きる特権を与えて来たモーセに、裏切られたと思ったことでしょう。イスラエルとエジプト、両方に属していると思ってきたモーセは、どちらからも徹底的に拒まれることになりました。ファラオの追手を逃れ、遠い異国の地ミデヤンまで来たモーセは、そこでミデヤンの祭司の家に身を寄せることになり、その祭司の娘の1人と結婚し、やがて二人のこどもにも恵まれました。
ミデヤンで暮らすようになって長い年月が経ちました。先ほどお聞きした使徒言行録では、エジプトから逃亡したのが40歳の時、そしてミデヤンの地での暮らしが40年経ったときのことが今日の出来事だとされています。使徒言行録が記された時代には、モーセの生涯を40年毎に三つに区切る捉え方が為されていたためです。その頃エジプトでは、これまでのファラオ、モーセを殺そうとしていたファラオは死にました。ファラオの代替わりの時でした。イスラエルの人々が自由を奪われ、苦役で支配されている状況はなおも続いていました。一方モーセは、エジプトから遥か遠いミデヤンで、イスラエルの民の一人としてでもなければ、神の民を苦しめるエジプト人の1人としてでもなく、寄留者としての日々を送っていました。かつてエジプトで、イスラエルの民の同胞であることも、自分が思う救いも正しさも退けられ、自分の存在と自分の行動の根幹にあると思って来たものが揺るがされたモーセは、そのようなことと向き合わずに済むミデヤンの地でどのような日々を送っていたのでしょうか。そのモーセにこの日、神さまが名前を呼んで、語り掛けてくださったのです。
神さまはモーセに、ご自分がどなたであるのか、炎と燃え尽きない柴とみ使いによって示されました。これらの特別なしるしはモーセに、神さまの言葉に耳を傾ける備えを為させることにもなったでしょう。モーセはこれらの不思議さに強く引き付けられ、近づこうとします。その時、神さまは呼びかけられました。息子イサクに刃物を振り下ろそうとしていたアブラハムに「アブラハム、アブラハム」と呼びかけられた時のように、また主の宮で眠っていた幼ないサムエルに「サムエル、サムエル」と呼びかけられた時のように、モーセの名を繰り返し呼ばれます。“全ての注意を私に向けなさい”、“これから告げることを受け止めなさい”、そう促しておられるようです。アブラハムが神さまに「はい、ここにおります」と応え、サムエルが「お話しください。僕は聞いております」と応えたように、モーセも神さまに、「み前におります」と応えます。これから神さまが何を語られるのか全く分からない中で、神さまのみ前に自分を据えて、神さまの言葉に聴き、神さまに従って行く備えが、モーセの中に為されたことを思わせる返事です。かつては自分の正義で身を固めていたモーセでしたが、長い年月がモーセに、神さまに従う力こそ必要であることを気づかせたのかもしれません。神さまの呼びかけによって、自分が神さまになり変わろうとするのではなく、神さまに従ってゆく歩みへと、モーセは立ち直すのです。
神さまに近付き過ぎないようにと、モーセは告げられます。距離は、神さまへの畏怖の念から生まれます。履き物を脱ぐのは、神さまに従う意思から為されます。当初、不思議な炎や燃えつきない柴に好奇心を掻き立てられたモーセは、神さまが聖なる方であることを、捉え切れていなかったように見受けます。神さまはモーセが好奇心の対象で終わらせられるような方ではなく、まことに聖なる方です。神さまの聖さが、この場所を聖なる地に変えています。神さまのために壮麗な神殿を建てたソロモンは、神殿を神さまに捧げる時にこう祈りました、「神は果たして地上に住まわれるでしょうか。天も、天の天も、あなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの神殿などなおさらです」(列王上8:27)。王が自分の持てる力を尽くして粋を結集した神殿でさえも、人が神さまをお入れする場所とはできません。神さまはそれほど聖なる方、遥か遠い方です。その神さまがホレブの山でモーセと会ってくださり、神さまの聖なる領域へと、招き入れてくださるのです。
そしてモーセにご自分はアブラハム、イサク、ヤコブの神であると言われます。この父祖たちを核としてイスラエルの民を興され、契約を与えられ、カナンの地で大いなる民とし、あらゆる民に神さまの祝福をもたらす祝福の基とすると約束してくださった神さまです。モーセも、神さまから祝福の基としての役割を与えられたその民の一人です。モーセも、父祖たちとそれぞれの時代の民が紡いできた信仰の歴史に立つ一人であることを思い起こさせ、そこに立ち帰らせる神さまの言葉であったことでしょう。
神さまの言葉によって、自分がどのような方の前に居るのかだんだんと分かってきたモーセは、炎や燃え尽きない柴やみ使いへの好奇心など吹っ飛び、神さまへの畏れから、神さまを直接見ないようにしました。神さまを直接見ることで、神さまの聖さや神さまの自由に踏み入ってしまわないようにと、そうしたのでしょう。
モーセにとっては、青天の霹靂のような出来事に思えたでしょう。しかしモーセには見えない、聞こえないところで、神さまのお働きが続いてきたことを、少し前から今日の箇所を見ると気づかされます。
今日の箇所の直前、2:23に、重い苦役を負わされていたイスラエルの人々が叫んだと記されています。国や地域の支配者の代が変わる時に、支配にゆるみが生じるのはいつの時代も同じでありましょう。前のファラオが死に、ファラオの交代期であるこの頃、生じた僅かな支配の隙間で、人々は叫ぶことができました。それまでの圧政は、あまりにも激しく、助けを求めて叫ぶ力すら人々から奪っていたのではないでしょうか。この時民は、苦しいと叫びました。苦役が苦しいと、人として生きる自由を奪われ、労働力にしか価値を見出されない者とされ続けることが苦しいと叫びます。この叫びがどこかに届くのか、それとも虚しく消えてゆくのか分からない、叫んだからと言って何かが変わるのか分からない、それでも肩に圧し掛かる建築資材の重さの下から呻き声を上げずにはいられない人々の声に、神さまは耳を傾けられました。神さまに届いていることをイスラエルの人々は知りようがありませんが、神さまはその呻きを耳にし、イスラエルの父祖たちと結んでこられた契約により強くみ心を向けられ、民を顧み、み心に留められました。助けを求める叫びに応え、契約をこの民においてご自分の言葉と行いに表すことへと動き始められたのです。
今日の箇所、ホレブの山でモーセに呼び掛けてくださった時も、神さまは同じことを同じように語られました。2章と同じ「見る」「聴く」「心に留める」という言葉によって、「私の民の苦しみをつぶさに見、追い使う者の前で叫ぶ声を聞いて、その痛みを確かに知った」と言われます。2章では神さまが「み心に留められた」とだけ述べられて、民の何についてみ心に留められたのかまでは明らかになっていませんが、モーセに対して、「民の痛みを確かに知った」のだとはっきりと述べておられます。2章では、み心に留めた、知った、そこまでしか述べられていませんでしたが、モーセにはその先を告げられます。降って行って民を救い出すと。2章では「イスラエルの人々」と呼ばれていた民のことを、モーセには「私の民」と呼ばれます。人々の苦しみ呻き痛みを、ご自分の民のこととして聴き、見て、心に留めてこられたことに気づかされます。この神さまが、ご自分の民を救うために、自ら民の所へと降ると言われます。み心に留めることに留まらず、地へと降られる方であります。使徒言行録の今日の箇所によって、神さまは人々に先立ってモーセの所へと降ってくださったことにも気づかされます。ご自分の民をエジプトの破壊的な支配から、人として生きる自由を奪っている地から救い出し、神さまが父祖たちに約束された地へと、神さまの約束が実現される地へと、神さまの祝福を共に分かち合うことができる地へと導き上るため、モーセの所へと降られました。
モーセは、出エジプトの出来事において、最も大きな役割を神さまから委ねられ、立派にその働きを担い通した人です。けれどモーセがその働きを担いたいと神さまに申し出たわけではありません。モーセから神さまに、ご自分の民をファラオの支配から救い出してくださいと、願ったわけではありません。寧ろモーセは、同胞からもファラオからも逃げて、エジプトでの現実から目を背けられるところに留まってきた者です。
神さまが出エジプトのみ業を為すことへとみ心を定められたのは、民の叫びがあったからでした。人々が助けを求めて叫んだからです。恐怖心や諦めや虚しさで呑み込まれそうな心を振り絞って叫んだ人々の声に、神さまが耳を傾けられたからです。自分たちの叫びが聴かれているのか、変わらず苦役を強いられ続けるこの日々を神さまが知っておられるのか確かめようが無い人々の一日、一日を、神さまがみ心に留めてこられたからです。民のところへ降り救い出そうとされる神さまの慈しみは、民だけでなくモーセにも注がれていました。モーセが願うことも求めることもなかった日々も、神さまの慈しみのみ心の中にあったのです。
自分の所まで降られた神さまに見えたモーセはこの日から、神さまと共なる生涯を歩み始めました。アブラハムは初めて神さまから呼び掛けられ、「自分が受け継ぐことになる土地に出て行くように召されたとき、これに従い、行く先を知らずに出て行」った、それは信仰によるのだと、ヘブライ書にあります(11:8)。これまでの親しい人間関係も、土地への愛着も、安定した暮らしも、それら自分のこれまでを後にして、それらと別れて出発したのは、神さまが共におられるからでした。その神さまに信頼したからでした。モーセが神さまの言葉に従い、ミデヤンでの居心地の良い暮らしと別れて出発し、かつて逃げ出した地へと、自分を拒んだ民の所へと向かうことができたのは、神さまが共におられるからです。自分のところにまで降られる神さまの慈しみと救いのみ業に、信頼したからです。
神さまはこの慈しみを、イエス・キリストにおいて最も明らかにしてくださっています。自ら願うことも、求めることもできない私たちを、ご自分に結び付け、救いを与え、他の人々とこの福音を分かち合う務めを担う者とするために、神さまご自身がクリスマスに人々の中に降られました。神さまをお迎えするのにふさわしいところなどどこにも造り出すことのできない私たちの中へと、聖なる方が降られ、私たちを人として生きることができない罪から救い出すために、私たちと同じ人となられました。地上の目に見える事柄だけで心が占められてしまう歩みと別れ、私たちの名前を繰り返し呼んでくださり、神の民として生きることへと導いてくださるみ子イエス・キリストの後に従って進みたいと願います。