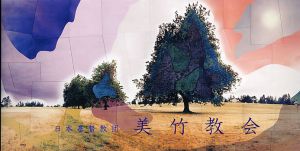「勇者たち」出エジプト1:22~2:10、Ⅰコリント1:26~31
2025年9月7日(左近深恵子)
エジプトでファラオに次ぐリーダーとなっていた息子ヨセフの力添えで、ヤコブは飢饉に見舞われていたカナンの地から家族とエジプトに移り住み、一族は生き延びることができました。そのヤコブの子どもたちの名前を述べることから、出エジプト記は始まります。創世記と同じ様に出エジプト記もヤコブのことをイスラエルと呼び、ヤコブの一族や子孫たちをイスラエルの子ら、イスラエルの人々と呼びます。ヤコブの12人の息子たちは、イスラエルの12部族の基となってゆきます。
ヨセフの活躍とヤコブたちのエジプト移住から長い年月が経ち、イスラエルの民もエジプトのファラオも世代が代わって行きました。かつて神さまがヤコブに約束されたように、ヤコブには多くの子孫が与えられ、イスラエルの民の数は増えていました。ヨセフが宰相としてエジプトにどんなに大きな貢献をし、エジプトの国力を強めたのか、イスラエルの民がなぜエジプトで暮らすようになったのか知らない新しいファラオは、イスラエルの民の存在に脅威を感じ、彼らが増えないようにあらゆる重い重労働を課して生活を追いつめるようにエジプトの人々に命じます。けれどイスラエルの民が苦役に耐え続け、数が減らないのを見ると、ファラオはシフラとプアという名前のイスラエルの2人の助産師に密かに、イスラエルの家族に生まれた男の子は出産時に殺せと命じます。しかし2人は出産の場で子どもを殺すようなことはせず、子どもの命を守り続けます。子どもが減らないのでファラオは2人を呼びつけ、なぜ命令通りにしないのだと問い詰めると2人は、自分たちは従うつもりで行くが、到着すると既に子どもは生まれてしまっているのだと返します。出エジプト記は、ファラオの命に従わない二人の行動の理由を、「助産婦たちが神を畏れていた」からだと述べています。そして二人についての記述の最後に、神さまがこの2人の家を栄えさせたことを述べ、その理由も、助産婦たちが神を畏れたからだと記しています。この国の全ての人間に勝る力を持つファラオから圧力をかけられる恐怖心の中で、勇気と知恵によって神の民の子らを守り、神さまから豊かに祝された2人の助産師を、聖書は二人の名前と共に大切に伝えてきました。
助産師たちを使って密かに子どもを減らす計画が進まないと、ファラオは今度は、生まれた男の子は一人残らずナイル川に投げ込むようにとの命令を国全体に出します。もはや密かにではなく、公然と、王が公に定めた政策として、イスラエルの家の男児を皆虐殺せよとの勅令を出したのです。イスラエルの民へのファラオの恐怖心と憎しみは、エジプトの地を覆ってゆきました。
イスラエルの人々を取り巻く混沌とした闇は、暗さを増してゆきます。ファラオは、隣人であるイスラエルの民との歴史に学ぼうとせず、イスラエルの民を労働力としてしか捉えず、結果、虐待し、抹殺しようとします。このファラオや、ファラオに追従する人々の姿が、リアルに聞こえて仕方ない今の時代です。このファラオは「ヨセフのことを知らない」者だと出エジプト記は最初に述べています。いつの時代にも、ヘイトを生む土壌には無知があることを思わされます。
ファラオの勅令下にあるこのエジプトで、レビの家出身の夫婦に一人の男の子が誕生します。レビの家とは、ヤコブの息子の一人、レビを基とする一族であり、後に祭司の務めを神さまから任じられる血筋です。祭司は、神さまと人々の間に立ち、人々の執り成しのために仕える者ですが、その働きはまさにこの子が大人になって果たす役割であることを、両親の血筋への言及によって思わされます。
母親は生まれた子が殺さなければならない男の子であると知った時に、どんな思いであったでしょうか。しかし子の愛らしさを見る内に心を決め、ファラオの命に従わず家に隠し育てます。やがて子は3か月を迎えます。これから益々成長する赤ちゃんをこれ以上家に隠しきれなくなった母親は、パピルスの籠にしっかり防水加工を施し、赤ちゃんを中に寝かせます。エジプトでは、衣類や食料など、日常使うものを蓋付きの籠に入れていたそうです。そのような籠であったのでしょう。赤ちゃんの入った籠をナイル河に運びます。ファラオが男の赤ちゃんを投げ込めと命じた河の畔に、流れに持って行かれないように水草の茂みに置きます。3か月と言えば、赤ちゃんの首がしっかりしてきて、授乳の間隔が定まり始め、子どもによっては昼間の授乳の間隔が開いてくる頃です。ここまで育ったのだから、ある程度の時間授乳無しで生き延びられことを母親は願ったのかもしれません。ファラオの脅威の下で押さえつけられ、混沌とした時代の流れに呑み込まれそうな、子どもをこれ以上自分の傍で守り続けるための手段を持たない一人の無力な母親ですが、子どもを諦めません。ナイル河に投げ込めと命じるファラオに子どもを渡しません。この母親は、少し先の系図では名前が述べられます。女性の名前が記録されることが決して当たり前でない系図に名前が記されていることに、神の民がこの母親の勇気と果たした役割を大切に受け止めてきたことが伝わってきます。しかしこの時点では、無名のまま語られます。王であるファラオに対し、虐待され、虐殺が命じられている民の一人の女性の無力さが際立ちます。その母親が心を決めた理由は、我が子が「愛らしかった」からだとあります。「愛らしかった」と訳されている言葉は、天地を創造された神さまが言われた「良かった」という言葉と同じです。混沌と渦巻く暗い水を分けて乾いた地を造り、被造物たち、そして人間をお造りくださった神さまは、お造りになったものをご覧になって、「良かった」と言われました。子どもの命と存在は、闇の中に光をもたらし、命と存在をもたらしてくださる神さまからの恵みです。愛らしさに溢れたその子は、神さまの慈しみと祝福に包まれています。この子をファラオではなく、知恵と勇気を尽くして神さまのご意志とお力に委ねた母親の行動は、祈りとも言えると思います。
母親同様、この段階では名前が記されていない、おそらく後のミリアムと思われるこの子の姉は、遠くから弟の身に何が起こるか見つめています。今にも籠の中に水が沁み込み始めるのではないか、衰弱が始まっているのではないかと、胸が潰れるような思いでこの時を耐えていた母親の思いを一心に受けて、姉は籠を見つめていたことでしょう。そこに、ファラオの娘が侍女たちを伴って現れます。ファラオの娘がそこで水浴びをすることを予測して、この子の母親が籠を置いたのかどうかは不明です。王女は一目見て籠の中の子がヘブライ人の男の子、つまりイスラエルの民の子であることに気づきます。イスラエルの民に恐怖心と憎しみを募らせているファラオと、その娘が同じ思いであっても不思議はなく、父王の命に従うのが当然の立場にいる王女が弟に何をするのか、弟に何が起きるのか、姉は固唾を飲んで見つめていたことでしょう。
王女は泣いている赤ちゃんを見て「不憫に思っ」たとあります。可哀そうだとどこか他人事として眺めているような言葉ではなく、「惜しむ」あるいは「責任を感じる」といった意味もある、強い感情を表す言葉です。生きるために必死に泣く目の前の赤ちゃんの命を惜しむ思い、防水した籠に込められた親の気持ちを思い、この子と出会った自分に何かできないかという思いかもしれません。しかしやはりここで名前が記されていないこの王女も、この子の命を救うには無力な者です。今すぐに手を打たなければ衰弱が進んでしまうこの乳児の命を守るための、知恵も知識も術もありません。王女の様子を遠くから見ていた姉は、王女に父王の政策に従おうとする気配が無いことを見て取ったのでしょう、この機会を逃してはならないと勇気を振り絞って王女の前に姿を現します。機転を利かせて、この子の乳母となれる人物を自分は知っていると申し出ます。目の前の子どもの命を救える具体的な手立てを思いがけず差し出された王女は、その娘の言葉に耳を傾け、心を決めます。父王の命令に従う道では無く、水から引き上げた子どもの命を守り続ける道を行くことを。
娘の申し出を受けて、王女はこの子の実の母親とは知らないまま、ヘブライ人の女性を乳母として雇います。イスラエルの民を祝福の基として選ばれた神さまの救いのご計画を知らなくとも、王女は目の前の子の命の尊さに胸を痛めるこころを持ち、命を奪えと命じる者が主張する正義は正義では無いと気づくこころを持っています。イスラエルの民を父王の手から解放することまでは望んではいなかったであろう無名の王女が、そうとは認識しないまま、イスラエルの民の将来の指導者とその民の未来を守ることに貢献するのです。
こうして、イスラエルの民の母娘とエジプト王女は、雇用関係とは言えこの子を守ることにおいて協力します。ファラオがあてがおうとしている敵意と恐怖心によって隔てられた関係に生きることを退けます。
子どもが十分成長すると、母親はその子を王女のところに連れてゆき、王女の養子とされ、「モーセ」というエジプト的な名前を付けられます。この名前自体はエジプトの王族によく見られる名前だそうです。エジプトの王族としてふさわしい名前を与えつつ、王女はこの名前に「私が彼を水から引き出したから」という意味を込めます。王女がモーセの命を救った出来事に、やがてモーセを通して神さまが神の民を水から救い、自由へと導かれた出来事が重なってゆきます。
モーセは、イスラエルの民の生まれでありながら、エジプトの最高権力者ファラオの娘の子として育てられます。王宮で暮らし、エジプトの王族たちが受けるエジプト最高の教育にも触れたのではないでしょうか。これらのことは後に、神さまによってイスラエルの民を導き出すために立てられ、ファラオやファラオの家臣たちと渡り合ってゆく中で、大いに役立ったことでしょう。
モーセの実の母親は勇気を振り絞り、知恵を駆使して、イスラエルの民にとっては正に死の淵と化していたナイル河からモーセを守ろうとしました。ファラオが追いつめる死から命への逆転を求めました。母親の行動が、虐殺する側にいる王女に、父王の命に従うよりこの子の命を守る行動へと押し出しました。母親と王女の行動が、弟を救いたい姉に踏み出す力と知恵を働かせる機転を与えました。姉の行動が王女に、自分たちエジプト人が人間扱いをしてこなかった民の若い娘の言葉に耳を傾け、知らぬまま実の母親を乳母として雇うことへと背中を押したのでしょう。父王の主張する正義ではない正しさに生きる王女の決断が、モーセの実の母親に我が子を養育することのできる貴い時間をもたらし、その上報酬として、つまりはファラオの財政から、子を養うために必要なものまで与えられました。これらの逆転の連鎖を遡れば、世の王の力よりも神さまを畏れた助産師たちも居ました。自分たちを覆う闇を引き裂く力も方策も持たない無力な助産師や、母親や、幼い姉、一人一人の神さまへの畏怖が、不条理な現実や恐怖を掻き立てる支配を超えて、神さまに信頼する歩みを支えたのでしょう。ファラオの目には低い者、無力な者、逆らうはずの無い者たちを通して、後にイスラエルの民を導く者となるモーセが救われました。ファラオの軍隊の装備に比べれば粗末で脆いパピルスの籠の中のこの赤ちゃんに、神の民の救いを託されました。ファラオにもファラオの民にも盤石に見えていた支配を逆転させる神さまへの畏れは、ファラオや人々の心が据えた厚く固く見える壁を越え、ファラオのすぐ傍に居る王女にまで届いたのです。
神の民の歴史において、この逆転は起こり続けました。神さまは、世でまかり通っている力、人々が本当はそこに正義を見出しきれていない、しかし世の趨勢となり続ける力、人が世に誇ることのできる力を用いるのではなく、力も根拠も無い者たちを通してみ業を為さいます。預言者イザヤもこう言います、「私たちが聞いたことを、誰が信じただろうか。主の腕は、誰に示されただろうか」(イザヤ53:1)。このような人に主のみ業が示されるはずがないと自分も周りも思っても、神さまを畏れる全ての者に勇者のような活躍の可能性が備えられています。残虐な、非人間的な支配がまかり通る時代に、数多の勇者たちを通して神さまは救いの御業を推し進めてこられたのです。
この救いは、イエス・キリストの十字架と復活によって決定的なものとされました。私たちを救うために、滅ぶべき罪を抱えた私たちではなく、独り子なる神が私たちの罪の値を負って死なれる、この逆転が、私たちを罪の滅びの淵から救い出してくださいます。私たちの誰一人このことを誤って自分が世にまかり通る力を持っているから、世に誇ることのできる正しさを持っているから、自分が他者よりも高みにいるからなどと思い、神さまのみ前で誇ることが無いように、神さまは世の愚かな者を選び、弱い者を選び、取るに足りない者を選び、軽んじられている者を選ばれたと、パウロはコリント書で述べます。神さまから召されたときのことを考え、神さまから与えられているものを見つめ直すようにと呼び掛けます。弱く無力な自分がただ神さまの憐れみと慈しみによって罪を贖われ、死の力に損なわれない命を約束されていることこそ、救いの確かさであることに何度だって力をいただきます。神さまの御業に用いられることを願って、知恵と力を注ぎ続けます。たった一人が何かしたところで焼け石に水だと囁く言葉に引きずられず、神さまの義のために何かができることを喜びます。神さまの義のために勇気と知恵をささげた信仰の先達たちの歩みを覚えることを大切にし、その歩みに続きたいと願います。