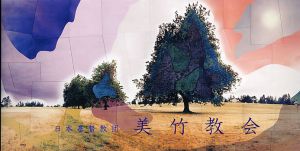2025.8.31.主日礼拝
イザヤ57:15-19、ローマ3:21-26
「人の義と神の義」 浅原一泰
先月末から十二日間、人工股関節を入れる手術を受けるために入院をした。入院してから三日目が手術の日。手術が終わった日は麻酔が中々覚めず、金属が入った腰も重く感じて痛みもあってかなり不自由に感じたが、次の日から毎日インストラクターが病室に来て、午前午後と一回ずつ丁寧にリハビリを指導して下さる日々が続いた。そうするうちに次第に痛みも和らぎ、人工関節が体に入った違和感も薄らいでいった。
その時の私の願いはただ一つ。一刻も早くこの病院から抜け出して退院する。そのこと以外にはなかった。リハビリではしばしばアンケートを書かされた。「痛みはどうですか」。「どんな時が一番苦しいですか」。「不安はありますか」。「実生活において具体的にどんなことが不安ですか」。そんな問いかけが並んでいた。「痛みはあるか」、「不安はあるか」という類の質問には、五段階か十段階のどれくらいかをチェックするように求められた。
その時私は何を思ったか。ただただ退院したくてたまらなかった私はうそをつきまくった。痛みなどない。苦しくなどない。不安などない。実生活において問題はない。そのような具合ですべての問いに対して、「一切問題はない」といった答えを貫き通したのである。よたよた歩きの段階であったにもかかわらず、自分の目的を達成するためならばと、あえて健康な人間のふりをしたのである。リハビリのインストラクターは笑みを浮かべながら探るような目で、「本当ですよね」と確認してきた。バレバレだったのだと思う。
でもこれは、人間の中に燻っている本性のようなものなのではないだろうか。高校生なら、実際にはまったく分かっていなくても、まったく興味も関心もない問いかけが実際に試験問題に出されたなら、誰だって、さも自分は分かっているかのように、さも昔から関心があってずっと考え続けて来たかのように答えを書こうとはしないだろうか。我々のような大人だって、つまらないと思っている話であっても、或いは立場が上の人から聞きたくもない話を長々と聞かされるような場合であっても、さも「分かります」と相手に見せるように、或いは相手に気に入られるように、うなずく素振りを見せてしまったことが誰にだってあるだろう。
人から認められたい。人に必要とされたい。多少の個人差があるだろうが、そんな風に心の中で思わない人間はいないのではないかと思う。誰だって認めてもらいたい、必要とされたいからこそ自分を良く見せようとする。誰からも羨ましがられるような人間に自分はなれないと分かってはいても、せめて分かってくれる親しい人たちからはいつまでも認めてもらいたい、と誰もが心の中で思っている。
有名なエデンの園の話を思い出して欲しい。あれは、神から命を与えられた初めの人間アダムとエバが神の言葉に背いた場面であった。住まいとして与えられたエデンの園にあるどの木からも取って食べて良いが、中央にある善悪の知識の木からは食べてはならない、食べれば死んでしまうと神が彼らに伝えたのに対して蛇は、食べても死なない、むしろ食べればお前たちの目は開け、神のようになれると囁いて、食べなければ損をするのはお前だと言わんばかりにプレッシャーをかけてきた。アダムもエバもその気になり、見るからに美味しそうなその木の実を食べてしまう。ありのままの姿を認められず、自分を偽ってでも自分を良く見せたい、高めたいという人間の欲求、それに付随する諸悪の根源は既にここに始まっていたと思うし、人間誰もがこのアダムとエバの子孫であり、そうである限りは世にある者すべて、例外なく誰もが、欲望や野心、自己中心というものに引きずられ、心が縛られて本当の人間らしく生きられなくなってしまっているのが現実だ、と聖書は教えている。与えられた命を、一度しかない人生を、花開かせるどころかむしろしぼむようにしか生きられない我々の状態。聖書はそれを、神に背く罪の生き方しか出来なくなっている、と説明する。
今日の説教題を「人の義と神の義」とした。先ほど読まれたローマ3章に出てくる「神の義」とは聖書にとって、またキリスト教にとってとても重要な意味を持っている。簡単に言えばそれは「神に良しと認められる」状態、と言ったら良いと思う。授業では「神の義」を私は、「神から必要とされることだ」と生徒たちに伝えて来た。そうであれば「人の義」とは誰かから、周りの仲間から、或いは組織の中であれば立場が上の人間から認められること、そのような人たちから、もっと大きく言えばその社会から自分が必要とされること、あなたはいなくてはならない大切な人間だと評価されること。そんな意味になるかと思う。そのために周到に準備を重ね、トライしては失敗を繰り返し、たまに上手くいくとこれで自分はもう勝利者であるかのように安心してはまた壁にぶつかって挫折を味わう。人間は誰もがおそらくそのような歩みを繰り返して年を重ねていく。
そうしているうちに何時かは自分が理想としている人間に近づけるのだろうか。求めている自分に果たしてなれるのだろうか。真っ正直に努力を重ね続けたその結果が必ず報われるとは、この世では言い切れないように思う。現実にはそこで様々な情報に振り回される。「こうすればいい」。「ああすれば必ず成功する」。言われた通りにしたって上手くいくわけがない。むしろ、複雑怪奇な人間関係の中でたまたま時の権力者に取り入って可愛がられるとか、力のない人間とは縁を切るとか、そんな処世術といったらよいのかあざとい知恵と言ったらよいのか、そういうものによって成功や勝利を掴んだ人間の方が多いように思う。
「人の義」がそうであるならば、「神の義」はどうであろうか。どうすれば神に良しと認められるような人間になれるのだろうか。500年以上前、この問題に真っ向から取り組んだ一人の修道士がいた。彼の名はマルチン・ルター。聖書には神が人間に与えた「律法」という大切な掟がある。殺してはならない。盗んではならない。姦淫してはならない。安息日を聖とせよ。そのような十戒の掟を中心として律法に細かい掟も含まれていた。それらを完璧に守ってこそ初めて人間は神から良しと認められる。ルターは人一倍努力して真剣に取り組んだが挫折する。神の掟を完全に守り抜くことなど出来ない自分自身をまざまざと見せつけられるわけだ。神は正義の神である以上、悪を許さない。そうであるならばどんなに努力しても自分は救われるどころか結局は滅ぼされ、呪われる。この恐怖に打ちのめされてルターは震えた。大事な試験が目前に迫っているのに納得いく準備ができていない状態。締切が明日に迫っているのに果たすべき課題が何も終わっていない状態。ルターが味わった恐怖は、そんな人間たちにも、いや、自分を良く見せるためには失敗を何とか防がなければならないというプレッシャーに囲まれている現代の人間すべてに降りかかっているもの、襲いかかっているものとそう遠くはないように思う。
ここで先ほど読まれたローマ3:21以下を振り返りたい。
しかし今や、律法を離れて、しかも律法と預言者によって証しされて、神の義が現されました。神の義は、イエス・キリストの真実によって、信じる者すべてに現されたのです。そこには何の差別もありません。
そう書いてある。「しかし今、律法を離れて現された」という神の義。それは、正義の神が敢えて人間の姿形をとって、イエス・キリストとなってこの世に来たことを指している。いと高き天におられる筈の神が、敢えて我々と同じ弱く脆い人間の姿となった。しかも世に来たそのイエスはこんな言葉を語っている。
「人の子は(「人の子」というのはイエスが自分の事を呼ぶ時の独特の呼び方であるが)、仕えられるためではなく仕えるために、また、多くの人の身代金として自分の命を献げるために来たのである」(マルコ10:45)。
神からこの世に遣わされた独り子なる神、悪を憎み善を愛する正義の神であり、世にある人間を裁く審判者である筈の神が人間イエスとなって世に来られた。しかしそれは仕えられるためにではなく仕えるために、罪に染まった人間たちの身代金としての自分の命を、つまり身代わりとなってご自分の命を捨てるためだ、とイエスは言った。失敗や過ちを犯した人間は必ずペナルティを受けなければならない。それは誰だって子供の頃から教え込まれている人としてのルールであろう。しかし同時に、失敗や過ちを犯すことなく、つまりペナルティを受けることなく最後まで生きられる人間などいるわけがない。偽ってでも自分を少しでも良く見せたいと常に考えている人間はそこでどうするかというと、失敗したのには理由があったのだともっともらしい言い訳を探し始める。同情を誘うためには涙まで流す者も現れる。判断を下す地位にある上の立場の人間には媚まで売って取り入る者もいる。「食べれば神になれる」。「こうすればあなたの罪は帳消しにされる」。そんな美味しい話に飛びつく者は後を絶たない。人の義の行きつく先はそんなところであろう。「私も悪かったが悪いのは私だけではない」。そんな言い訳、責任転嫁を繰り返すばかりで、自らが犯した罪や過ちに対して責任を取る者など一人もいない。そのような人間は死の裁きを受けねばならないと聖書は言う。死は避けられない。誰もその裁きから逃れられない。
しかし今や、律法とはまったく無縁の神の義がイエス・キリストにおいて現れたと聖書は語っていた。続けて聖書はこう語っている。
「人は皆、罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっていますが、キリスト・イエスによる贖いの業を通して、神の恵みにより値なしに義とされるのです。神はこのイエスを、真実による、またその血による贖いの座とされました。」
つまり、全ての者が受けねばならない死の裁きをキリスト・イエスが身代わりとなって受けたということだ。支払わなければならない借金や負わねばならない裁きを誰かが代わりに背負うことを贖いという。キリストは、神に背く罪を犯して救われなくなっている人間すべてのために身代わりとなって十字架の刑に処せられ、血を流された、ということだ。神が世に送った独り子なる神が、である。世にある人間を裁く権威を持つ神が、である。裁かれるべき我々人間すべての代わりとなって神が裁かれる。そのことを聖書はこう説明する。
「それは、これまでに犯されて来た罪を見逃して、ご自身の義(神の義)を示すためでした。神が忍耐してこられたのは、今この時にご自身の義を示すため、すなわち、ご自身が義となり、イエスの真実に基づく者を義とするためでした。」
正しい者を救い、悪に走る者を滅びへと突き落とす裁きが「神の義」なのではない。分かっていても、どうしても過ちを繰り返し、悪に手を染めてしまう人間の罪をこれまで見逃し、忍耐し、遂には神自らが人間イエスとなって彼ら罪ある人間すべての代わりに死の裁きを受ける。そこまでしてでも何とかして人間一人一人を義とする。一人一人を良しと認め、一人一人を必要とする。それが神の義なのだと。今や、キリスト・イエスに証しされて現された神の義なのだと。
その神の思いを預言者イザヤもこう語っていた。
「彼(人間)の貪欲の罪に私は怒り、彼を打ち、姿を隠して怒った。しかし彼は背いたまま、心の赴くままに道を歩んだ。私は彼の道を見た。」
しかしそこで彼を裁くのではない。「私は高く、聖なる所に住み、打ち砕かれた人、低められた人と共にいて、低められた人の霊を生き返らせ、打ち砕かれた人の心を生き返らせる」と。「私は彼を癒やし、導き、慰めをもって彼とその悲しむ人々に報い、唇に賛美の実りを創造しよう。遠くにいる人にも近くにいる人にも平和、平和があるように、私は彼を癒やそう、主は言われる」と。
500年前、この神の義が、恐怖に打ちのめされていたルターの目を開いた。「正義を貫く人間を祝福し、悪に走る人間を滅ぼす」のが「神の義」なのではない。神の義は律法の中に示されるのではなく、全ての者を救いへと招く福音の中に現されている。それはユダヤ人であれギリシア人であれ、信じる者すべて、つまりそれに気づかされた者すべてに神が与えようとしている恵みであるのだと。それが神の義である。そこには何の差別もない。人間が媚を売ろうとふてくされた態度を取ろうと関係ない。それを受け取るために人間が前もってしなければならないような課題も条件も一切ない。求められていることはただ一つ。迷うことなく、疑うことなく、心を開いて神から与えられるものを受け止めることだ、と。それに気づいたルターが、感動の余りに溢れる涙を抑えきれない体験をしたことからあの宗教改革は始まって今に至っている。
二千年前だけの話ではない。五百年前だけの話でもない。今なお神に背き罪を犯している我々すべてのために、同じ過ちを繰り返す将来の人間のためにも身代わりとなってキリスト・イエスは十字架の死の裁きを受けている。それは本来、我々が受けなければならない裁きである。しかも神はキリストを十字架にかけることで、我々の中の悪しき部分をも十字架にかけている。我々の悪しき命をも十字架で滅ぼしている。しかし神はキリストをよみがえらせた。死で終わることも裁かれることもない永遠の命へと起き上がらせた。それも、本来ならば死の裁きを逃れられない我々のためである。その命を我々に得させるため、我々を新しい命へと生まれ変わらせるためにキリストは身代わりとなることを選んだのである。
それが神の義である。罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっている我々人間すべてを、キリスト・イエスによる贖いの業を通して、神の恵みにより値なしに義とする神の義である。
それを受け取るために果たさなければならない課題も条件もない。求められているのは、心を開いて受け止めることだけである。今のあなたがどういう状況にあろうと神はこれを与えようと手を差し伸べている。この神の義は人間を様々なプレッシャーから、恐怖から解放してくれる。自分らしく生きる自由に目覚めさせてくれる。今日、この神の義が一人一人に惜しみなく注がれたことを信じて、この神の義を受け止めて、新しい命の道を共に歩み出したい。