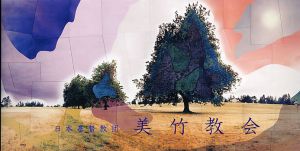「先の者が後に」創世記25:19~26、Ⅰコリント1:26~31
2025年8月6日(左近深恵子)
アブラハムの物語を礼拝において聞いてきました。神さまはアブラハムから大いなる民を興し、その民を通してあらゆる氏族にご自分の祝福をもたらすと約束されました。アブラハムから始まる神の民に、神さまは、他の人々にも祝福をもたらす、神さまの祝福の器となる役割を与えられたのです。不妊のため子を望むことができず、既に高齢になっていたアブラハム夫婦に、大いなる民へとつながる子ども、イサクを与えてくださいました。アブラハムは、イサクが大人になると、家の財産すべての管理を任せているほど信頼を置いている僕を、イサクの結婚相手を探すため、自分の故郷の地に遣わします。僕は、アブラハムの故郷ハランの地に近いパダン・アラムという町に着くと神さまに祈ります。すると祈りが終わらない内にリベカと出会うことができ、リベカがアブラハムの親族であることも知ります。リベカの家族に主人アブラハムが自分を遣わした理由を告げると、リベカの親も、この結婚話が、神さまの導きによるものであると受け止め、結婚に同意します。しかし僕が早速次の日リベカを伴って町を発とうとすると、両親はもう少し家族のもとに娘を留めて欲しいと頼みます。親として当然の願いではありますが、僕は、この旅の目的を叶えてくださったのは主であるのだから、人の思いで日を送らせてはならないと主張します。互いに譲れない状況を打破したのは、リベカの決断です。リベカは、僕と共に今日出発すると告げます。祝福を担うことを神さまから託されたイサクの歩みに一時も早く合流することが自分の取るべき道だと潔く決断したリベカには、見えないこの先を神さまに信頼してお委ねする真っすぐな熱意が感じられます。
けれどその後イサクとリベカの家庭には、子どもに恵まれない日々が長く続きます。この箇所の聖書の言葉によれば、ほぼ20年に渡ります。子孫が増え、大きな民となって、祝福を他の民にもたらすという神さまから委ねられた使命を担うはずでありながら、次の世代が与えられない日々です。僕が告げる神さまの導きに信頼し、会ったこともないイサクと結婚するために、翌日には家族も故郷も後にして、未知の土地へと旅立ったリベカの熱意と覚悟を思うと、それ以来祝福を受け継ぐ子が与えられないまま過ぎてゆく日々はあまりにも酷に思えます。イサクとリベカの夫婦にとって、この年月は神さまへの信頼が揺さぶられる危機ともなり得たでしょう。しかしイサクは、神さまに祈り続けていたのです。
今日の箇所は、「アブラハムの子イサクの系図は次の通りである」と述べることから始まっています。これはイサクの家族の物語です。しかし何章にも渡って語られる物語に耳を傾けると、イサク自身よりも他の人々の存在感の方が大きく感じます。イサクが自ら行動を起こす姿は数えるほどしか語られません。その数少ない箇所の一つである今日の箇所が伝えるイサクは、祈りの人です。妻リベカのために祈り続けます。その間リベカも、道が拓かれない苦しみに耐え続けます。祝福を受け継ぐ大きな民となることが神さまから約束されている夫婦であり、リベカには、行き詰まった状況を打開するほどの主への信頼と熱意があります。しかし、彼らの熱意や力が、神さまの祝福を担う道を切り拓かせるのではありません。祝福を与え、道を与え、命を与えられるのは神さまです。自分たち家族の主は神さまです。イサクは、夫婦の願いが現実とならない年月、約束を与えられた神さまは、必ず約束を実現してくださる方であると信頼し、神さまのみ前に思いを注ぎ出しながら、忍耐強く祈り続けました。親の役割は主に祈ることから始まり、願いも苦しみもただ神さまに注ぎ出し、神さまの御業を祈り求めながら、イサクは親とされてゆきます。神さまはイサクの祈りを聞き入れられ、リベカは身ごもったのです。
子どもが欲しいと願い続けてきた夫婦に子どもが与えられた、これこそ神が祈りに応えられるということだと、私たちはすっきりするかもしれません。ようやく神さまが、祝福を担う民となるとの約束を実現へと一歩前進させてくださったと、神さまのみ心とみ業が分かったと、納得するかもしれません。
しかし神さまのみ心もみ業も、人の思いを超えるものです。子を宿した喜びも束の間、リベカは喜びを上回る苦しみを味わうことになります。胎動は母親にとって妊娠の苦労を吹き飛ばしてくれるような特別な喜びでありますが、リベカの胎動は、激しい痛みを伴います。どうやら自分の胎内には一人ではなく複数の子どもが宿っていると、その動きからリベカは分かったのでしょう。「押し合う」と訳されている言葉は、イザヤ書では葦と言う植物が折られる表現に用いられますが、士師記や詩編では頭蓋骨を打ち砕くことを表す言葉です。最も多くこの言葉が用いられるのは、貧しい人々が抑圧されている様を表す表現においてです。葦を折るような、頭が砕かれるような、押しつぶされるような激しい胎児たちの動きです。それはリベカの生死に関わるほどのものであったと取る人もいます。今以上に妊娠・出産に母体の危険が伴った時代、リベカにとってその痛みは確かに深刻な不安となったでしょう。自分の体や胎児の成長への不安であり、自分たち家族のこの先への不安であったでしょう。命の与え手であり、約束を実現してくださる神さまが扉を開いてくださったと思っていた道なのに、再び扉が閉じられてゆくような不安に苛まれたのではないでしょうか。
リベカが取った行動も、祈りでした。不安を神さまのみ前に注ぎ出し、神さまのみ旨を求めるため、リベカは祈ることのできる場所に行きます。聖所のような所でしょうか。そこで神さまはリベカに語り掛け、こう言われました。「二つの国民があなたの胎内に宿っており、二つの民があなたの腹の中から分かれ出る」。
神さまは「二人の子どもがあなたの胎内に宿っている」とは言われず、「国民が」「民が」と言われます。アブラハムに約束されたように、リベカの胎に宿る二人の子の子孫が民となってゆくことを示されます。二人の子どもが一つの民の始まりとなるのではなく、二つの民へと分かれてゆくと、そのうち一方が他方よりも強くなるのだと言われます。そして神さまは、二人の子の人性に二つの民を重ねるように、兄は弟に仕えるようになると言われます。
今日の箇所は「アブラハムの子イサクの系図は次の通りである」との言葉から始まっていました。ここからイサクの家族の歴史が綴られてゆく、その初めに神さまは、弟ヤコブから始まるイスラエルの民の流れと、兄エサウから始まるエドムの民の流れにこの家族が分かれてゆくことを告げられます。リベカの胎動の苦しみが子を宿す喜びの中にあったリベカを不安で覆ったように、神さまの言葉も、リベカが願った神さまの答えとはまったく違うものであったことでしょう。子どもたちが複数の民の始まりとなることだけだったら、ただ喜びであったでしょう。その二つの民は、力も立場も等しいものであり、両者が共に一つとなって、祝福を受け継ぐ一つの流れを形成してゆくと神さまが言われたのなら、更に喜びとなったかもしれません。等しい民となるのは難しくても、兄の民が祝福を主に担い、弟の民もそれに倣って歩むようになると言われたとしても、家族のこの先に抱いていた不安は消えていったかもしれません。
けれど神さまは、一方を祝福を担う器とされると、それは弟から始まる民の方であると、兄から始まる民は、祝福を受け継いできた自分たち家族の歴史を知ってはいるものの、核となって祝福を担う民とはならず、弟の民に従う民となると告げられます。リベカの期待や想定とは異なる祝福の道筋が、告げられたのです。
二人の子は、胎児であった時から互いに、共にいるには狭すぎる存在となっています。双子の争いは、この先も続いてゆきます。エサウは生まれ出る順番争いに勝って、先に誕生し、兄となりました。ヤコブは争いに負けて弟となりましたが、エサウ1人先に行かせるものかと言わんばかりに、最後までエサウの踵を掴んで出てきました。神さまからの言葉を何も知らない母親の胎にいた時から、命にかかわるような激しさで争っていた二人です。一方が強くなり、他方がそれに従う、それも兄が弟に従うという神さまのご計画によって、二人の争いはこの先より深刻さを増し、殺意まで生じさせるものとなってゆきます。アブラハムから神さまの祝福を受け継ぎ、次世代へと祝福を引き継ぐのは、このような家族であります。そして、双子の内ヤコブの方を祝福を受け継ぐ者とされるのは、神さまのご意志によります。祝福の器とされることに誰もが納得するような秀でた素質が、エサウよりもヤコブにあったわけでもありません。このことをパウロはローマの信徒への手紙でこう記しています、「私たちの先祖イサクと結ばれたリベカの場合もそうでした。まだ子供たちが生まれもせず、善いことも悪いこともしていないのに、『兄は弟に仕えるようになる』とリベカに告げられました。それは、神の選びの計画が行いによってではなく、お召しになる方によって進められるためでした」(ロマ9:10~12)。良い行いをしてきたから、信仰深く、正しく生きて来た者だから、神さまはヤコブを選ばれた、そう言われるならば納得しやすい私たちにとって、神さまの選びは理解し難い、躓きに満ちたものです。このことを告げられたリベカは、驚き、困惑したことでしょう。
リベカはこの先、ヤコブを祝福の担い手とすることに大きな役割を果たすことになります。長子が家を継いで当然とする世の秩序を踏襲しようとするイサクは、エサウを祝福の担い手としようとします。エサウも、自分がイサクの後を継いで祝福を受け継ぐのが当然と考えます。そのようなイサクやエサウと対立をしてでも、リベカはヤコブに祝福を継がせようとします。リベカをそうさせる根拠は、激しい痛みの中で聞いた神さまのこの言葉にあるのではないでしょうか。神さまの言葉ではないものを頼りにする者の言動は、祝福を担う働きの妨げとなってしまうこともあります。しかし人は、神さまの救いのご計画にお応えし、従うことができる者です。人がどのように信頼をもって応えるのか、その言動によって、祝福を担ってゆく働きに貢献することができます。
神さまは、エサウを否定しておられるのではありません。全ての人に神さまの祝福に与かる可能性が開かれていることを、否定しておられるのでもありません。人の中にある相応しさが、人を祝福の担い手とするのでは無いと言うことです。世の価値基準によって、神さまの祝福の継承者が定められるのでも無いと言うことです。あらゆる民に祝福をもたらすことを願われる神さまは、その祝福のご計画を、ただ神さまの選びによって、ただ神さまの恵みと赦しのみ心によって、推し進められます。
先ほど、Ⅰコリント書のパウロの言葉を共にお聞きしました。パウロは危機の中にあるコリントの教会の人々に、主の言葉を受け止めて欲しいと願っています。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かなものですが、救われる者には神の力だからです。主のみ言葉を受け入れる手掛かりは、自分の上に起きた主の御業を思い起こすことです。だからパウロは先ず、「あなたがたが召された時のことを考えてみなさい」と語りかけます。あなたがたが召された時、「世の知恵ある者は多くなく、有力な者や家柄のよい者も多くはい」なかっただろうと。人は自分の知恵を誇っている限り、神さまの救いを受けとめる器となることは非常に難しいのです。力や地位を誇っている限り、自分の力を頼みとし、自分の力によって思いのままに生きることができると思うのです。自分自身を他の者よりも上に立つ主としている限り、主が救い主であることが分からないのです。神さまからいただいてきたものを考えれば、人の知恵も能力も地位も、貧しい不完全なものに過ぎないことを知ります。神さまの恵みの豊かさを知ると、神さまからいただいているものの大きさ、深さ、広さを証したいと願います。しかし、自分の知恵や力を尽くしても、全て体現できる人はいません。寧ろ、無学な者、無力な者を神さまは福音の器としてお立てになります。自分の不完全さ、自分の無力さを知る者は、主に祈り、主に救いを求めることに近くいる者です。自分の力を頼みとする者は、自分が罪ある者であること、自分が救いを必要としている者であることを受け入れること、主に心から助けを祈り求めることに遠い者です。パウロは、「召された時のことを考えてみなさい」と述べていました。考えるのは、自分が救いを獲得した時のことでも、自分が救われることを了解した時のことでもありません。人の目や世の価値判断にからめとられていた状況から神さまが導き出してくださった時のこと、罪から救いの中へと招き入れてくださった時のことです。自分の強い希望によってでもなく、自分に救われる資格があったからでもなく、神のみ子が自分の罪の値を代わりに払うために十字架にお架かりくださったから、主の祝福を受けとめる器となることができるのです。
私たちは、自分の知恵や力の貧しさを案ずる必要はないのです。キリストが私たちの知恵となってくださり、キリストが義と、聖と、贖いとなってくださっているからです。神さまは私たちの誰一人神さまの前で誇ることが無いように、ただ主を誇る者となるように、世が愚かだとする者、弱いとする者を祝福の担い手としてくださいます。私たちの命と存在と思いと行いの値の高さは、キリストによって与えられるのです。
ヤコブは、後にイスラエルと呼ばれるようになります。神の民の名前が、イサクの次男、ヤコブにおいて明らかになります。生まれ出る前から兄弟と争いを始めていたような者であり、世が重んじる長子という立場にはなれなかったこのヤコブを、神さまは祝福を担う器として立てられました。このヤコブを、アブラハム、イサクと続いてきた神の民の系譜に続く者とされました。ヤコブのように私たちも、自分の思いや意志の強さによってではなく、能力や資質やそれまでの行いの正しさによってではなく、ただ神さまのみ心によって救いへと導かれてきました。ただ主なる神だけを誇りながら歩めることの幸いを、共に感謝したいと思います。