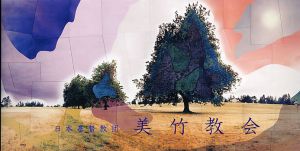「願うことができる」創世記18:20~33、ロマ3:23~24
2025年7月20日(左近深恵子)
神の民とされた人々、後に神さまからイスラエルという名前をいただくことになる民の始まりに、神さまが選び立てられたアブラハムという人について、このところ創世記から聞いています。12章に、初めて神さまがアブラハムに語り掛けられた出来事が記されています。そこで神さまは、アブラハムから大きな国民を興し、祝福すると約束されました。アブラハムは祝福の基となるのだと、言われました。アブラハムに神さまの祝福を見出だし、その祝福を求める人々も神さまは祝福され、そうして地上の全ての民がアブラハムによって祝福の中へと招かれるのだと、約束されました。アブラハムは神の民の歴史の初めに立つ者とされましたが、それは神さまがあらゆる人々へともたらそうとされる祝福の道筋の出発点に立つことでもありました。神の民が自分たちに至った救いの歴史を振り返る時、それは祝福の歴史であり、その始まりに、神さまから祝福の基とされたアブラハムが居るのです。
神さまは、地上の人々の間に、歴史を貫いて祝福の道を通してゆくため、アブラハムとアブラハムから興してくださる民に、その道を守る務めを与えられます。今日の箇所の少し前で神さまはこう言われています、「私がアブラハムを選んだのは、彼がその子らとその後に続く家族の者たちに命じて、彼らが正義と公正を行い、主の道を守るようにするためであり、主がアブラハムに約束されたことを成就するためである」(18:18~19)。この言葉は、神さまがアブラハムに、アブラハムと妻サラの間に来年息子が生まれると告げられた出来事の後に述べられています。これまで神さまがアブラハムに約束して来られた、アブラハムを大いなる民とするとの約束の実現の第一歩となる、息子の誕生です。自分たちの年齢や状態からは子どもを望めないアブラハムとサラに、ただ神さまからの恵みとして子どもが与えられます。その子どもから更に多くの子孫が与えられることも神さまは約束しておられます。かつては、子を望めない自分たち夫婦で、自分たち家族の歴史は閉じられると思っていたアブラハムに、神さまが、その先の歴史を与えてくださいます。神さまが興し、導いてくださる民の歴史がここから始まります。この民は、ただ神さまから命を与えられ、人数を増し加えられた集団となるのではなく、神さまの道を守る役割があります。アブラハムには、後に続く者たちに、神さまの正義と公正を行い、主の道を守るように命じる役割があります。そうすることで、アブラハムと後に続く者たちは、神さまにお応えし、神さまへの信頼においてこそ一つとなる信仰の共同体であることを求めることができます。この信仰の民の歩みを通して、神さまがアブラハムに約束されたように、あらゆる民に神さまの祝福がもたらされるのです。
この頃アブラハムは、死海の西側に広がる山地の高台で暮らしていました。そこに主なる神が来られ、来年息子が生まれると言われ、そして、ソドムの町の罪が極めて重いと訴える叫びが神さまに届いているから、下って行って、その叫びの通りかどうか確かめると言われたのです。神さまは既にソドムの町の人々の罪がどのようなものであるのか、その罪がどれほど深いのか、よくご存知であったことでしょう。この町の罪の故に、神さまに向かって叫ばずにはいられない人々の苦しみを重く受け止めておられる神さまは、ただ噂を確認するようにソドムの町の罪深さを確認するためだけに行かれるのではなく、罪に対し裁きを下すため、町を滅ぼすことを見据えておいでになったのでしょう。
人々を苦しめたソドムの罪とはどのようなものであったのか、エゼキエル書にはソドムについてこのような主の言葉があります、「高慢で、食物に飽き、安閑としていながら、苦しむ者や貧しい者を助けなかった。高ぶり、私の前で忌むべきことを行った」(エゼキエル16:49~50)。死海沿岸にあり、鉱山も抱える豊かな町であったソドムは、大きな利益を生み出す鉱山を巡って争いが絶えない地域でもありました。イザヤ書にもソドムについて記している箇所がありますが、そこでも、孤児や寡婦といった、共同体の中で弱い立場にあり、経済的に乏しい者たちを守ることが正しく行われておらず、強い者たちはそのような者たちを搾取しながら、神さまへの犠牲をささげることや祈りを捧げることは盛大に行っている町の様子が述べられています。そして預言者は町の支配者たちに対して、主の言葉に聞けと、そのようないけにえを主は喜ばない、善を行うことを学べ、公正を追い求め、虐げられた者を救えと告げています(イザヤ1:10~17)。ソドムの町で富や力を手にした者たちは、その豊かさや安定した暮らしを主に感謝することもなく、乏しい者を助けようともせず、隣人を苦しめているのに自分たちが為すべきことを為そうとせず、自分の体裁を繕うためなら形ばかりの礼拝を捧げることも恐れない、神さまを畏れない者たちでありました。ソドムの悪の本質にあるのは、神さまとの関係の破れでありました。
神さまは、わざわざアブラハムに予告せずとも、ソドムを滅ぼすことができる方です。アブラハムに告げられたのは、アブラハムに与えておられる役割の故でありましょう。後に続く者たちに正義と公正を行うことを命じることで、神さまの道を守り、世のどのような力よりも神さまを畏れ、何よりも神さまに信頼する民をつくる務めをアブラハムに託しておられます。アブラハムにソドムのことを告げることによって、後に続く者たちに先立って、アブラハム自身が、神さまの義と公正を求める在り方を考えることを願っておられるように思えます。それは、神さまご自身も、裁きだけを願っておられるのではないからではないでしょうか。敢えて町に行って確認などしなくても、町の罪深さをご存知である神さまが、下って行って、罪に浸りきった人々の中へと入って行き、人々の現状を一つ一つ確かめようとしておられます。確かめずには、滅ぼす決断ができないと思っておられます。滅ぼす決断をしなくても良い何かを人々の中に見出したいと、願っておられるからではないでしょうか。
神さまは、伴っていた二人の者が先にソドムへと向かって行っても、ソドムの町が遠く一望できるその場所で、アブラハムの傍に留まってくださっていました。アブラハムが考え、何かを願うことを待っておられたからではないでしょうか。自分と共に留まってくださる主の御前にアブラハムも立ち続け、そして神さまのみ前に更に一歩進み出て、町を滅ぼすことを思いとどまってくださいと訴え始めたのです。
アブラハムは、ソドムの町の人々の罪がそこまで重くないと見て、思いとどまることを求めたのではありません。神さまが裁きをなさることを、否定しているわけでもありません。神さまとの関係が破れ、関係の回復を自ら求めることもできず、滅びと自ら転げ落ちているような町に対して、神さまが裁きを下されることは正しいことであります。裁きは、神さまが為されることであり、神さまこそ、裁くことのできる方です。人間の悪を曖昧にせず、徹底して裁かれるのは、神さまの義しさにふさわしいことです。
それでもアブラハムが神さまに問わずにはいられなかったのは、町の人々の中に正しい者がいるかもしれないと思うからです。悪が神さまとの関係の破れであるように、正しい者とは、罪が無いことを言うのではなく、神さまとの関係において正しく在る者です。その正しい者が悪い者と一緒に滅ぼされることを、問うています。
アブラハムの訴えは、それまで、神さまの裁きにおいて当然とされてきたことを問うものでありました。悪い者が居るならばそこに神さまの裁きが下り、そのことで他の人々が巻き添えを食らうことは仕方がないとされてきました。アブラハムが問うのは神さまの正しさです。神さまの義が為されることです。悪を抱えてきた共同体が皆共に責任を負うことだけが正しさなのですか。正しい者を悪い者と同じ仕方で扱い、正しい者と悪い者が同じような目に遭うことは、神さまの公正な裁きなのですかと。決して悪を曖昧にされず、ソドムの町のような悪に対して裁きを下されることは、神さまの義にふさわしいことであります。それでも神さまは、アブラハムのこの訴えを遮らず、耳を傾けておられます。
アブラハムは言葉を続けます。もし私たちがアブラハムであったなら、ここで発するのは、正しい者たちは滅ぼさず救い出してください、との願いではないでしょうか。悪い者は裁かれるべきだが、正しい者は裁かれてはならないと。けれどアブラハムの主張はそうではありません。50人という具体的な人数を挙げて、町全体を覆う悪の闇の大きさに比べれば、決して多くは無いこの人数であっても、その正しい者たちのためにお赦しくださらないのですかと問うのです。すると神さまは、もし50人正しい者がいるなら、その正しい者たちのために、その町全体を赦すと言われるのです。50人の正しい者たちを救い出して、残りの者たちを滅ぼすと言われるのではなく、町を赦すと言われるのです。
既に裁きを見据えておられた神さまが、アブラハムの訴えに耳を傾け、意向を変えてくださいました。けれどアブラハムはそこで終わりにしません。正しい者の人数を、50人から5人引いて、問い直します。45人と言わずに「50人に5人足りない」という表現によって、さっきお赦しくださった50人のケースと大した差は無いと、印象付けようとしているようにも見えます。知恵を尽くして交渉するアブラハムの姿が思い浮かびます。神さまは、45人でも滅ぼさないとお答えになります。するとアブラハムは、40人だったら、30人だったらと人数を減らしながら神さまに求め続けます。途中から減らす人数を5人から10人に増やしている所に、神さまに迫るアブラハムの勢いも見受けられます。3度の繰り返しは聖書の中でよく見られます。しかしアブラハムは4回、5回と願いを重ねます。執拗とも無遠慮とも言える繰り返しですが、アブラハムは主に対してその都度敬意を表し、控えめに、丁寧に前置きをしながら願います。願いを重ねる毎に、神さまのお答えに神さまの憐れみの深さを知り、謙虚さを増してゆきます。そうしてとうとう3度の繰り返しの2倍、6回も願いを述べたのです。
アブラハムのこの執拗とも言える嘆願は、自分のためではなく、自分の属する共同体のためではなく、その町のほとんどの人の顔も名前も知らない民であり、まして悪行の数々で有名な、神さまに従う生き方に背を向けて来た人々が多く含まれている民のためであります。その人々に対して、神さまの正義と公正が行われるためであります。そのために必死に食い下がって訴え続けるアブラハムの執り成しの願いを、神さまは認めてくださっています。このアブラハムの姿に、いつの時代の神の民も、私たちも、神さまが祝福の基とされ、祝福の道の出発点とされた者の在り方を見出すのです。
アブラハムに続くことを願いながらも私たちは、まるで神さまに正しさとは何であるのか教えるかのように、何度も繰り返し願うアブラハムの姿に、戸惑いを覚えるかもしれません。アブラハムがこのように願うことができたのは、アブラハムが立派な人間であり、正しさとは何であるのか主張できるふさわしさを持つからではありません。アブラハムは自分が「塵や灰に過ぎない」者であると深く自覚しています。これまで危機に見舞われると神さまに信頼しきれなくなり、現実に頼れるのは自分だと、神さまに背を向けて自分の力や可能性に頼って道を切り開こうとし、神さまが与えてくださった契約を自分の方から見限るようなこともしてきたアブラハムです。けれど神さまは、そのような神さまとの関係に破れていたアブラハムを見捨てず、神さまの元に立ち返るように導き、契約を結び続けてくださいました。この神さまに、神さまの正義と公正を求めて真っ直ぐな思いを率直に注ぎ出すならば、神さまは耳を傾けてくださり、受け止め、応えてくださるとの信頼によって、アブラハムは願うのです。
アブラハムが10人までくいさがったところで交渉が打ち切られたことにも、私たちは戸惑いを覚えるかもしれません。ここまで頑張ったのなら1人までくいさがって欲しかったとの気持ちが残るのではないでしょうか。アブラハムは、神さまがそれ以上の交渉を望んでおられないことに気づいたのかもしれません。あるいはこの先は、自分が追及してはならないことだと、最後の最後にどうなさるかは神さまの領域なのだと、思ったのかもしれません。神さまはアブラハムと語り終えると去って行かれ、アブラハムは自分の住まいに帰って行ったとあります。
そもそも自分は、正しい人が1人しかおらず、他の者は皆、神さまに背き続けている町に、赦しを願うことができるのかと考えさせられます。そもそも裁きと赦しを考える時に、いつの間にか自分を正しい者の側に置いてしまっていることに気づかされます。神さまに苦しみを訴え叫んだ人々の立場からばかり、この出来事を眺めがちです。そこに自分を置き続ける限り、他者に多大な苦しみを負わせ、正しい者の言葉に耳を傾けない人々の中にたった一人正しい者が居るからと言って、その人々が裁きを免れることを、心の底から願うことは難しいのではないでしょうか。
自分を正しい者の中にではなく、神さまとの関係に破れてきた者の中に自分を見出す時、この出来事の情景は違って見えてきます。神さまに裁きを下すことを思いとどまってくださるようにと必死に願うアブラハムの訴えが、自分のための言葉に聞こえてきます。アブラハムに応えられた、「正しい者がいるならば、その者のために滅ぼさないことにしよう」と言われる神さまの言葉に、赦しの希望を見出します。
パウロはローマの信徒への手紙で「人は皆、罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっていますが、キリスト・イエスによる贖いの業を通して、神の恵みにより値無しに義とされるのです」と述べています。キリスト・イエスは、ご自分を父なる神が遣わされた救い主として受け入れず、ご自分の言葉に耳を傾けず、ご自分を十字架上の死にまで追いやった人々のために、神さまの義が成し遂げられるために、神のみ子ご自身が自らを犠牲のささげものとしてくださいました。このただお一人、真に義なる方の死が、私たちの罪を神さまが赦される理由です。決して悪を曖昧に見過ごすことをなさらず、悪に対して徹底的に裁きを下される神さまの義と、神さまに背を向け、悪に自分自身を支配させてしまっている者たちを忍耐をもって赦して救おうとされる神さまの憐れみが、十字架でのみ子イエス・キリストの死となりました。私たち自身がキリストの贖いが必要な罪人であることに気付かされるのです。
私たちも主のみ前に立ち続けましょう。主の御前に進み出て、罪の赦しを祈り求め、キリストが私たちのために命を捧げてくださったことに感謝し、神さまから赦しと祝福をいただいていることの喜びと驚きを噛みしめるところから、私たちの一歩が始まります。神さまの正義と公正を行い、他者のために執り成しの祈りをささげ、そうして主の道を守ることに参与する私たちの一歩が始まるのです。