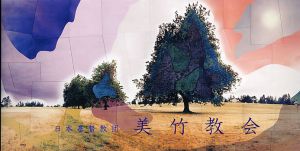「望みの言葉」創世記1:1~5、ヘブライ11:3
2025年5月4日(左近深恵子)
先週の夕礼拝では、ヨハネの黙示録の最後の部分を聞きました。黙示録は、主が初めであり終わりであるのだと語ります。そのことが、黙示録の初めにおいても、終わりにおいても告げられ、黙示録全体のメッセージであることを示しています。黙示録は、教会に対する苛烈な迫害が起こっている地域の諸教会に宛てて、教会の礼拝において朗読されるために書かれたと考えられています。キリストの後に従う者として生きて行こうとすることが、命や肉体や生活を危険に晒し、積み上げてきたものが否定され、奪われかねない危機の中にある人々に、今在る者とされ、信仰に生きようとしていることを遡っていくとその初めにおられるのは主なのだと語ります。それ以上に黙示録は、終わりにおられるのも主なのだと伝えることに注力しています。キリスト者たちを迫害する力を持つ者たちが終わりではなく、死が終わりではなく、神さまが、キリストが、終わりであるのだと、終わりの時に、主なる神にまさって裁くことができる者はいないのだと告げます。この神さまが私たちの主であるのだと、危機の中にある今も、私たちと共におられるのだと、黙示録の言葉を信仰者たちは礼拝で聞いたことでしょう。
今年度は暫く礼拝で旧約聖書の言葉を中心に聞いてゆきます。そして本日は、創世記の初めの箇所から聞きました。創造について語る創世記の冒頭の部分も、ヨハネの黙示録のように危機の中にある人々に対して書かれ、礼拝の中で朗読されるために書かれたのだと考えられています。「初めに神は天と地を創造された。地は混沌として、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。神は言われた。「光あれ。」すると光があった。」情景や動きを細やかに描き出すような言葉が何もない、最低限に絞られた簡潔な文章の言葉が、礼拝で一語一語、朗読者の口から発せられるのを聞く人々の心に、言葉が一つ一つ響いて行ったことでしょう。危機の中で人は普段は考えずに済むようなことを考えないわけにゆかなくなります。この状況の中で自分は何を源とすべきなのか、この状況の終わりには何があるのか、自分たちは何を見つめてこの時を耐えるのか、今、神はこの時を共にしておられるのか、そのような自分の存在、自分の大切な人の存在の根源にあるものを考えずにはいられません。そのような人々に対して紡がれた言葉は、時代を越えて、根源にあるものを問う心に響き続けます。
創世記の最初の聞き手となった人々が味わっていたのは、信仰の中心であり生活の中心であった神殿を失い、ダビデ王朝を失い、仲間たちを失った危機でした。書かれたのは、紀元前の6世紀、バビロン捕囚の時代であっただろうと言われています。既にイスラエルの王国は分裂し、北王国は滅び、南王国ユダだけとなっていましたが、そのユダ王国が大国バビロニア帝国に侵略され、エルサレムの都も神殿も破壊され、ダビデ王朝も滅亡させられたのでした。支配国バビロンは、ユダ王国の民の中から、支配者層にいた人々、バビロンにとって有益な技能を持つと見做された人々、その地にそのまま残しておくとバビロンに敵対する勢力となってゆく恐れがあると判断した人々を、捕囚として強制的に自国に移住させました。捕囚とされた人々がそこから引き剥がされた地は、神さまから約束の地として託され、ダビデが王として立てられ、ソロモンが神さまを礼拝するために神殿を建て、神さまがその神殿に臨在されることを約束された地でした。その地で共に主を礼拝し、共に生活をしてきた他の民からも引き離され、その軍事力、経済力や文化の繁栄に目を見張らずにはいられない支配国に連れてこられました。支配国の民から、“お前たちの神は一体どこにいるのだ”と嘲られながら、その民が拝む神々の巨大な偶像を目の当たりにする日々が続くうち、やがて捕囚として連れてこられた世代は次々とその生涯を終え、故国を見たことが無い世代へと変わってゆきます。バビロン帝国のユダ王国に対する勝利は、バビロンの神々のイスラエルの神に対する勝利だと捉えるのが常識であった世界の中で、“お前たちの神は一体どこにいるのだ”との嘲りに、自分たちも大きく信仰の足元を揺るがされてしまう思いであったでしょう。目に見える証拠を突き付けて反論したくても難しい状況で、揺るがされないように歯を食いしばって堪え続ける苦しみがあったことでしょう。バビロンの人々に同調する流れに引き寄せられそうな魂の危機もあったことでしょう。人々にとって現実は混沌であり、底の見えない深淵へと流されてしまいそうなものであったでしょう。
創世記は「初めに神は天と地を創造された」と告げます。この世界はバビロニア帝国の支配によって存在しているのではない、バビロニア帝国の民の嘲りが全てを支配しているのではない、イスラエルの民がこの世界を始めたのでもない、ダビデ王朝が始めたのでもない、今あること、この地に存在し、命を与えられて生きていること、やがてそれぞれの生涯に死が訪れること、それら全ての始まりに、神さまのみ業があることを告げます。エルサレムの都も神殿も破壊され、祭儀に用いられてきた大切な祭具は奪われ、故国から遠いこの異国の地では、神殿の残骸どころか、神殿が建っていた場所すら見ることも触れることもできません。神さまが今自分たちと共におられ、今も御業を為しておられるしるしをなかなか見出せないでいる。それよりも視界に入ってくるのは支配国の繁栄と、帝国の民が崇める偶像の巨大さであり、耳に入ってくるのは、“お前たちの神は一体どこにいるのだ”という嘲り。この混沌の中に置かれている人々にも、神さまは言葉によって語り掛けてくださいます。“初めに、神が、天と地を創造された、あなたがたも、神がお造りになった”のだと。
「地は混沌として、闇が深淵の面にあり」との言葉を捕囚の民は、今自分たちが味わっている現実と重ねて聞いたことでしょう。私たちにとっても決して遠い言葉ではありません。災害による甚大な被害があります。災害によって社会の歪みや欠けが露わになり、そのための苦難までも強いられ続けている人々がいます。人の目に露わになっていない歪みや欠けの中で人知れず苦闘している人々は、どんなに多いことかと思います。戦争や紛争に巻き込まれ、苦難の中にある人々が大勢いることを知りながら、その人々を苦しみの中から助け出す道を見出せない危機の中に、私たち皆が居るとも言えます。
一人一人、それぞれに特有な苦難もあります。自分が置かれている状況を思う度に心が沈むような時があるかもしれません。先が開けて見えるようになって欲しいと願うのに、目が覚める度、淀んだ状況の中で今日1日も生きて行かなければならないことに心が沈んでゆく日もあるかもしれません。能力や生産性が世を動かす最大の力だ、全ての創造の原動力だと捉え、そのような力を発揮できることが人の存在の価値だとする風潮があります。そのように価値を示すことができない人を透明人間のように扱い、人として存在していないかのように見做す風潮に、自覚のないままどこかで馴染んでしまう危機が絶えず私たちにあるのではないでしょうか。混沌としている状態は、混沌としたまま、濁り続けてゆきます。「混沌」という言葉は「形なく、空しい」とも訳されます。全体に破壊され、形を取っていない、被造物がその中で生きていくために必要な形を取ろうとしない、まとまらないまま混沌とし続ける、空しい状態です。この言葉は聖書では、道無き荒れ野で迷い、死に至る状況を指すものとしても、よく用いられます。荒れ野の中に神さまの道を通すことに抗い、神様の導きを拒む状態とも言えます。預言者イザヤは45章で、神さまの創造のみ業とそこに現れたご意志、そして神さまの言葉をこう伝えています、「天を創造された方、地を形作り、造り上げ、固く据えられた方。地を空しくは創造せず、人の住む所として形作られた方。主はこう言われる。私は主、他にはいない。私は隠れた所や闇の地で語ったことはなく、ヤコブの子孫に『混沌の中に私を探し求めよ』といったこともない。私は主、義を語り、正しいことを告げる者である」(45:18~19)。神さまは、人がその言葉を聴きたくても聴くことができないような隠れた所で語られる方ではない。闇が支配する地で闇からの言葉として語られる方でもない。神さまの導きを拒み、神さまの道によってまとまることを拒み、淀み濁り続けようとする者たちの中に、ご自分を探し求めよと言われる方でも無いのです。言い換えれば、人には、神さまをそのような所に探し求めてしまうところがあるということでしょう。混沌とした深い闇は神さまの住まいではありません。神様はその混沌にも深淵にも呑み込まれる方ではありません。その中で苦しむ人々に、語り掛けてくださる方です。
「深淵」と言う表現は、死を指し示します。適度な量の清い水は人の生命を維持します。しかし深淵は、死に至らせる力として聖書に多く登場します。深淵として、目の前に広がる深い海のような領域を想いうかべることもできますが、この創世記の箇所では地の底に横たわる海がイメージされているのかもしれません。大地の底で、人々を呑み込まんと静かに暗い水を湛えている見えない深淵があるとの世界観を、古代の人々は持っていたと言われます。固く揺るぎないものに思える大地の下にあるかもしれない深淵を、人々は恐れていたのかもしれません。大地の下に人知れず広がる暗く深い水の力は、人にとって圧倒的な存在です。どんなに健康に恵まれて喜び多い人生であっても、死の力は人の日々に陰を落とします。しかし闇に覆われた深淵の水の面を、霊をもって、あるいは息を持って、風をもって、動き回ることのできる神さまは、この深淵の力からも自由な方、混沌とした深淵にも闇にも勝る方であるのです。
深淵の水面の上を動き回る神さまの霊は、み子イエス・キリストの地上の歩みを思わせます。神のみ子は闇が広がる世に人としてお生まれになり、人々の中に住まってくださいました。み子は闇の中、混沌の中に降られ、その中に留まることができる方です。しかし闇は、世の光なるキリストを呑み込むことも、自分に属させることもできません。み子は、神の国の到来、神さまのご支配の到来を告げるために、自由に町や村を訪ねて回られました。そのみ子を大勢の人が求めました。悪霊と呼ばれる神さまに背かせる力に支配されて来た人々、病に日常も人生も破壊されて来た人々、その家族たちが、主イエスの行く先々に主を求めて集まってきました。混沌の力をも支配される神さまのお力が、の方と共にある、この方を神さまがお遣わしになった、そう信頼したからでありましょう。捕囚の時代も、新約聖書の時代も、そして現代も、混沌とした状態の中にいる私たちに、この世界が本来どのようなところであるのか、創世記は教えます。世界は、神さまが「光あれ」との言葉によって造られた、神さまの光から形を取り始めたところであると。
神様は、闇に覆われ光が無いところに、光をもたらされました。光によって、闇と光を分けられました。創造は新しいものを作り出すことだけではありません。まとまろうとしない形無く空しい状態に、神様の義しさをもたらし、その正しさによって秩序立てることであります。第一に神さまの臨在とみ心を表すものとして光をもたらされ、闇と光を分けられました。次に、水の力を上と下に分け、次に、生き物が生きて行くための大地を自ら分け、こうして順に分けることを重ねてゆかれます。この箇所の言葉を礼拝で聴く一人一人が、神さまが言葉によって光や自分たちの存在をもたらされたことを知り、言葉によって神さまが何を何から分けられたか、神さまがもたらしてくださった秩序はどのようなものであるのか、知ってきたことでしょう。自分たちも何から何を分けるべきなのか識別する目を与えられ、自分たちの生活の中で神さまのみ心に従って分け続けてゆくことを求める生き方へと導かれます。ヘブライ書にあるように、「信仰によって、この世界が神の言葉によって造られ、見えるものは見えるものからできたのでは無いことを悟り」ます。「光あれ」と告げられた神さまの言葉によって、自分の日々も神さまの光を求めることへと礼拝から踏み出します。
神様は、混沌と混じり合っていた闇と、ご自分が世にもたらされた光を分けられました。そして光を見て良しとされました。創造の一つ一つの御業は、神さまのご意志と、良しとされる神様の喜びに溢れています。造られたものはみな、その存在を願われる神さまのご意志の内に存在することへと招きだされ、そうして存在を与えられたものが願われた通り良いものであることを喜ばれる神さまの喜びに包まれます。自分や圧倒的な力を持つものの願いや目的が初めにあるのではなく、自分が自分を良しとしたから、あるいは誰かが良しとしたから、存在することができているのでもないのです。
神様は光と闇にそれぞれ、昼と夜と名前を与えました。名前を与えるということは、名付ける相手に対して力を持っていることを意味します。混沌とした状態を覆い隠す闇に夜という名前を付けるということは、闇に対して神さまが支配者であることの宣言とも言えます。名付けることによって、闇の力は全てを覆うことができず夜という役割の中に留められると、神さまが定められたと言えます。依然として混沌も闇も、私たちの日々において力を持ち続けています。けれど神さまはそれらに勝る方であることを知ります。神さまが夜という役割を闇に与えてくださったことによって、闇が力を発揮できる時間には必ず終わりがあり、朝がやって来ることを知ります。闇が人の視界を遮り、覆い隠している混沌とした力も、深淵の水面を動くことができ、闇に名前を付けることのできる神様には全て露わになっています。詩編139の言葉を思い起こします、「闇もあなたには闇とはならず/夜も昼のように光り輝く。闇も光も変わるところがない」(139:12)。闇の内に起きていることも神さまの前では光に照らされるように顕わになっています。神さまは全てをご存知であることが、私たちの希望です。そして私たちの内にある闇との親和性も全てご存知であり、その上で、その罪の闇をみ子キリストが十字架の死によって滅ぼしてくださったことが、私たちの救いです。