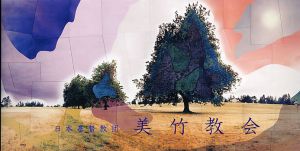「独りではない」詩編34:9~11、ヨハネ21:1~14
2025年4月20日(イースター礼拝・左近深恵子)
私たちが思い描く喜びとは、どのようなものでしょうか。楽しくて嬉しくて気持ちが高揚してくる、わくわくするような喜びがあります。あるいは、あなたはそのままで良いのだと、よく頑張って来たねと何もかも肯定してくれる、居心地の良い温かさを感じさせてくれる喜びもあります。喜びとはそのようなものなのだと思い、喜びをその枠の中でばかり考えがちな耳に、十字架と復活の出来事は、すぐには喜びの調べを奏でません。十字架は、罪赦されないまま死を死んで行くしかない私たちの代わりに、イエス・キリストが死んでくださった出来事です。復活は、3日に渡って死を死に通されたイエス・キリストが、死者の中からよみがえられた出来事です。十字架の死よりも、死からよみがえられた復活の方がまだ、その報せを喜びと受け止めることができるかもしれません。けれど、自分の思う喜ばしさの枠の中で喜んでいるならば、それは復活の恵みを受け止めきれていることになりません。マグダラのマリアがそうでした。この福音書は、復活された主イエスが最初にマグダラのマリアにご自身を現わしてくださったことを伝えます。マリアは主イエスの遺体が納められた墓に行ってみると空になっていたので、急ぎペトロと「主イエスが愛しておられた弟子」と呼ばれる弟子のところに行って、「誰かが主を墓から取り去りました」と伝えます。また墓に戻って、空の墓の傍で泣いていたマリアに語り掛ける方があります。初めはその方が誰か分からなかったマリアですが、自分の名を呼ばれて、復活された主イエスであることを悟り、「先生」と答えます。その時主はマリアに「私に触れてはいけない」と言われます。マリアが主に触れようとしたからでありましょう。主の復活を、生きておられるその体に触れることで受け止めたい、そのように触れることができる喜びの範囲で捉え、その喜びの内に留まっていたい、一対一の関わりの内に留まっていたいと思う気持ちはよく分かります。しかし主イエスは、復活をそのような枠の内に留めさせません。マリアに、弟子たちの所へ行って、主イエスが父なる神のもとに上ることを伝えなさいと命じます。直ぐにこの言葉に従ったマリアは、復活の最初の証人となります。主の言葉に従うことを通して、主が復活された喜びとは、手が届く範囲に留まらない、主に従ってきた者たち全ての喜びであるのだと知り、その喜びをもたらす働きを担う喜びも味わったことでしょう。
主はその後、一所に集まっていた弟子たちに、ご自分を現してくださいました。その場にいなかったトマスのためにも再度、弟子たちの所に来てくださいました。復活の知らせに大きく動揺し、自分が正しいとする枠で事態を理解しようとするトマスの頑なさは、復活の主との出会いによって砕かれ、「私の主、私の神よ」と、主イエスへの信仰を告白しました。人を死に至るまで支配する罪の力も、全てを断ち切る死の力も、み子の復活によって神さまが打ち破られたのだと、死を超えて私の主であり私の神である救い主が生きておられるのだと、トマスは深い喜びに内側から満たされ、喜びは信仰の告白となって溢れ出したのでしょう。死者の中から復活された主は、私たちの初穂となられたのだと知る喜びを、弟子たちは味わい始めたことでしょう。
これらは、主が十字架にお架かりになったエルサレムで起こりました。今日の箇所は、ガリラヤでの出来事を伝えます。ティベリウス湖とは、ガリラヤ湖の別名です。そこに居たのは一番弟子であるペトロ、復活の主に信仰を告白したトマス、ナタナエル、ゼベダイの息子たち、それに他の2人の、計7人でした。その内、少なくともペトロとゼベダイの息子たちの3人は、かつてこのガリラヤで漁師をしていました。この日彼らがティベリウス湖で漁をしたのは、弟子となる前の生活に戻ろうと故郷に帰り、以前の仕事に戻ったからだと読むこともできるでしょう。しかし、主イエスは十字架にお架かりになる前の晩、晩餐の席で弟子たちに、「私は復活した後、あなたがたより先にガリラヤに行く」と言われています。彼らはその主の言葉に従ったからガリラヤに居たのではないか。弟子となる前の生活にすっかり戻ってしまったのではなく、主によって互いに結び付けられた弟子として一つとなって行動していたのではないか。だから出身地が同じではない者も一緒にいたのではないかと、考えられるのです。
共に活動する彼らの姿も、魚を取るというだけでなく、主の弟子としての姿があると、多くの人が受け止めてきました。漁という仕事に、主イエスが与えてくださった言葉も思い起こされます。かつてペトロは主イエスから「私に付いて来なさい。人間をとる漁師にしよう」と言われ、主に従い始めたからです。人間をとる漁師として、人々をキリストのもとへと招く弟子たちの在り方が見えるように思うのです。
他の場面でそうであるように、先ず最初に言葉を発し、思ったら即行動するのはペトロです。「私は漁に出る」とのペトロの言葉に他の者たちが、「私たちも一緒に行こう」と応えます。そうして彼らは夜の湖に舟を漕ぎだし漁をしますが、この湖を知り尽くしているベテラン漁師が何人もいる彼らが一晩中網を打っても1匹も捕れません。彼らの姿を、復活の主が岸辺から見つめておられることに気づかないまま、悪戦苦闘を続けます。彼らは声を掛けられ、どなたであるのか分からないまま、言われた通りにします。それは、舟の反対側に網を打つということだけであるのに、網を引き揚げられないほど大量の大きな魚が捕れます。その収穫をもたらした方は主イエスであると最初に気づいたのは、マリアの知らせを聞いてペトロとお墓に走ったあの愛弟子です。この人は、ペトロより先に墓に到着し、先にお墓の中をのぞいて空であることを確認した人であり、その後でペトロがお墓の中にまで入って主イエスを巻いていた布の位置などを確認しました。この福音書では、ペトロと並ぶ重要な存在としてしばしば登場します。思ったことを真っ先に口に出し、直ぐに行動に移すのがペトロならば、大切なことを最初に認識し、受け止めるのはこの人でした。今日の出来事でも最初に復活の主がおられ、主が漁に大きな成果をもたらしてくださったことに気づき、ペトロに教えたのは愛弟子であり、それを聞いてペトロは上着を纏い、舟も魚も後にして、湖に飛び込んで主イエスのもとに急ぎます。湖に飛び込んで泳げば服から何から濡れてしまうのに、主イエスに対する敬意から、今できる最大限で身を整えようと、上着を纏わずにはいられなかったのでしょう。逮捕され連行される主イエスの後を大祭司の中庭まで追って行ったものの、主イエスとの関係を問われ、主イエスを知らないと三度も繰り返してしまった者として、上着を纏わずに主の前に出ることができなかった、舟が岸に着くのを待てず、とにかく主の元に急がずにはいられなかったペトロの思いもあったのかもしれません。
しかしまた、舟に引き上げることができないほど大量の魚を網ごと、舟で何とか岸まで引いていった他の弟子たちの骨折りがあったからこそ、捕れた魚は収穫となったことも思わされます。弟子たちにはそれぞれの思いと表し方があります。ばらばらに見える一人一人が、ただお一人の方に従うために、それぞれの心と力を注ぎ、そうして互いに補い合い、主の弟子の働きとされてゆきます。全ては、復活の主がおられることで始まります。彼らは魚を捕るために漁に出ましたが、主がおられないところ、主のみ言葉に従っているのではないところでは、どんなに経験と技能と知識と熱意と時間を注いでも、一匹も魚は取れませんでした。最も自分たちの力を発揮できるはずの状況であっても、自分たちで自分たちを必ず養うことができるわけではないのが、弟子たち、私たちです。自分の得意分野であろうと素人同然の者であろうと、キリストに従いたいという願いが同じであるから共に進もうとするのであり、そうして向かって行く所はそこが故郷であろうとどこだろうと、キリストが遣わされた場所であります。私たちには共に支え合う、ただキリストによって結び付けられている友があり、私たちを結び付け、遣わすキリストがおられます。キリストは私たちの出発点であり、私たちが帰るところです。この日弟子たちは、湖畔で炭火を起こし、朝食を用意して待っておられるキリストの所へ、収穫を携えて帰ります。主イエスは肉体だけでなく内なる飢えを、満たしてくださいます。主の弟子として福音に生き、福音を宣べ伝える歩みも、聖餐の食卓から受けるキリストのパンと盃によって養われつつ進む旅であります。
ティベリウスと言う湖の名前が言及されるのは、この福音書で二度目です。一度目は、6章の五千人の群衆を養われた出来事です。6章でも、主はパンと魚で人々の空腹を満たされました。肉体の飢えを満たすだけでなく、こう言われました、「朽ちる食べ物のためではなく、いつまでも留まって永遠の命に至る食べ物のために働きなさい」。人は何かのために働いたり奮闘しながら生きてゆきます。朽ちる食べ物のためではなく永遠の命に至る食べ物のために、奮闘しなさいと言われます。そして、「神のパンは、天から降って来て、世に命を与える」「私は天から降って来たパンである」と言われて、十字架でのご自分の死と聖餐の意味を示されました。
その出来事と重なるように、復活の主も、ティベリウス湖の岸辺でパンと魚をもって、疲労困憊の弟子たちを養います。「パンを取り、弟子たちに与えられた」「魚も同じようにされた」という表現も、五千人の供食の出来事の語り口と重なります。朽ちる食べ物のためではない道へと一人一人を遣わされる主イエスは、その奮闘を見守り、み言葉で道を示し、朽ちない食べ物で養ってくださいます。主の食卓で、私たちを待っておられます。主イエスの十字架は、私たちの罪と、罪赦されぬまま死んでゆくしかない死を滅ぼし、私たちを朽ちない命にいきることへと導くためであったのだと、主イエスは、罪の闇にも押し潰されない、死の力にもかき消されない命を養ってくださる天からのパンなのだと、聖餐の食卓に着く度に、何度でも驚きを与えられます。糧をいただいてようやく、自分は飢え渇いてたのだと、疲弊して弱っていたのだと気付かされます。弟子たちはエルサレムで既に復活された主イエスにお会いしていたのに、まるで初めて復活の主にお会いしたかのように驚き、主が備えてくださった朝ごはんによって満たされています。主は生きておられるのだ、自分たちの罪や死が困難をもたらす時も、生ける主は自分たちと共におられ、自分たちを養ってくださるのだと、何度だって気づかされるのです。
今為していることは徒労に終わるのではないか、この辛さや悲しさは何になるのだ、結局死によっていつかは消えてしまうのではないか、そのように死の力に抗えない日々の中で疲弊している私たちに、キリストは何度もご自分は生きておられると教えてくださり、糧をもって養ってくださいます。弟子の群れである教会の礼拝においてこそ、ご自身を現わしてくださり、聖餐の糧を持って養ってくださいます。詩編34編が「味わい、見よ、主の恵み深さを」と呼び掛けているように、そう呼び掛けられなければ受けている恵みを味わおうとしない私たちです。感情を楽しませ、喜ばせるものを追い求めるだけでなく、弟子たちが網の中の大きな魚を数え上げたように、いただいてきた恵みを一つ一つ数え上げ、感謝を新たにする幸いがあります。共に復活の主が招いてくださる聖餐の食卓で、主の恵みを共にいただき、その度に新たな喜びと力と気付きを与えられる幸いがあります。