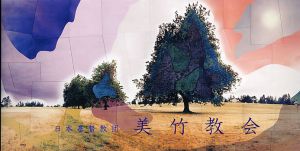「十字架を背負う主」イザヤ53:11~12、ヨハネ19:17~27
2025年4月13日(レントⅥ・左近深恵子)
主イエスは過越祭の時が訪れると、「この世から父の元へ移るご自分の時が来たことを悟り、世に居るご自分の者たちを愛して、最後まで愛し抜かれ」たと、ヨハネによる福音書は伝えます。そして、ご自分にとって最後となる過越の食事の席で弟子たちの足を洗われました。師である主イエスが弟子である自分の足を洗うなんて、とペトロが止めようとすると、「私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる」と言われました。足を洗われることで、神さまの愛がどのようなものであるのか、身をもって示してくださいました。神さまの愛は、汚れた人を洗い清め、ご自分との関わりを回復してくださいます。もうすぐ弟子たちの傍を去ることになる主イエスは、“師であり主である私があなたがたの足を洗ったのだから、あなたがたもこの愛に生きなさい、互いに足を洗い合いなさい”と彼らに告げられました。
その食事の席でペトロは主イエスに、「あなたのためなら命を捨てます」とも断言しました。ペトロは“この方のためなら命も惜しくない”、そう自分の人生を捧げられる方を見つけることのできた自分の目にも、その主イエスに従い通す自分の意志の力にも自信がありました。その晩、逮捕され連行された主イエスを追って大祭司の中庭に来たペトロは、主イエスとの関係を問われると、自分の身が危ういかもしれないという恐怖に陥ったのでしょう、関係を否定し、主イエスとの繋がりを自ら退けました。ペトロが自信を持っていた判断力も強い意志の力も、いざとなれば脆いものでした。けれどペトロがご自分を否定することを主イエスは知っておられました。ご自分の者たちを愛して、最後まで愛し抜かれる主イエスは、ペトロが「あなたのためなら命を捨てます」と言った時も、大祭司の庭で主イエスとの関係を否定した時も、ペトロを見捨てておられませんでした。ペトロのように、従うにふさわしい方としてキリストを見出したのは自分であるように思い、キリストとの繋がり、神さまとの繋がりは自分の意志の力や熱量にあるのだと捉えがちな私たちです。神さまの愛は、私たちの中の、神さまから愛を注がれるに値する相応しさに依るのではないことをなかなか認めようとしない私たち一人一人を愛し抜かれるキリストを、十字架の出来事こそ明らかにします。
逮捕された主イエスの尋問と裁判は、ユダヤの指導者たちと、ローマの権威を代表するローマ総督ピラトによって行われました。ユダヤの指導者たちは、主イエスの力も存在も封じ込めたいのであり、総督は自分の領地で騒動が起こることを避けたいのであり、しかしどちらも主イエスを殺す責任は負いたくないため、それぞれがその責任を相手に押し付けようとします。有罪とする罪が主イエスに無いことを知りながら、保身のために主イエスを無罪にしないピラト。十字架という異邦人の処刑法で、ローマの権威の元で主イエスを処刑させようとする、主イエスご自身も属するユダヤの民の指導者たち。そして指導者たちの判断を黙認し同調する群衆。一人一人が主イエスを見捨て、主との関わりを退ける度、人々は主イエスを死の淵へと追い遣りました。ペトロやこの人々の闇が、自分の中には一切無いとは決して言えない私たちであります。
主イエスはもし望めば、ご自分を死へと追い遣る一つ一つの動きを押し返すこともできたでしょう。天地創造の物語は、混沌とした暗い深い水の流れを押し留めて、乾いた地を造られ、被造物が生きていくことができるようにしてくださり、その世界に私たちを生かしてくださる神さまのみ業を語ります。出エジプトの出来事は、死んだも同然のように扱われていた古代イスラエルの民を奴隷の地から導き出された神さまが、行く手を阻む葦の海の水を押し留めて乾いた道を造り、追手から守り、民に命と自由を回復してくださったことを伝えます。み子も、ご自分を十字架に追いやろうとする人々を押し留め、ご自分の命を守る道を確保しようと願えばそうすることのできるお力を持っておられる方でありましょう。けれどみ子は、人の罪が混然一体となってご自分を呑み込もうとする中、十字架に至る道を進み続けてくださいました。この罪の闇の中にも、死のただ中にも、人が神さまと繋がり続ける道を通すために、されこうべを意味するゴルゴタという処刑場に、ご自分が架けられる十字架を背負い、向かわれました。背負っておられたのは十字架の横木であっただろうと言われます。死刑囚に十字架の横木を背負わせて刑場に引いてゆくのが、ローマの習慣であったからです。
ゴルゴタという所へ「向かわれた」とあるのは、ゴルゴタがエルサレムの都の外にあり、都を出てそちらに向かったということでありましょう。生きている人々のための都を出て、罪人たちを死に引き渡す処刑場へと、罪無き方が向かってゆきます。晩餐の席でペトロは、自分の足を主イエスが洗うことに対して、“そのようなことは私がするべきことで、先生であり、主であるあなたが私の為にすることではありません”と、止めようとしました。しかし、処刑場に向かう主イエスを止めようとする者は誰もいません。洗足を通してその意味を示されていながら、弟子たちは、主イエスを見捨てて逃げてしまっています。あるいは口を噤んでいます。晩餐の時主はペトロに、「私のしていることは、今あなたには分からないが、後で、分かるようになる」と言われました。弟子たちは復活の主にお会いして、またペンテコステの日に降られた聖霊のお力によって、十字架の意味が分かるようになっていったことでしょう。自分の罪の重さを正面から見据えることができない私たちも、神さまの導きがあって初めて「分かるようになる」ことであります。神の独り子が背負っておられるのは自分の罪の重さであること、み子がそのために命を捧げてくださらなければ赦されない重さであることを受け留められず、そこまでの赦しが自分に必要であることを認められず、その赦しを自ら願うこともできない一人一人のために、主は都を後にし、十字架を背負ってゴルゴタへと向かってくださいました。
ゴルゴタには3本の十字架が立てられ、主イエスは他の2人の死刑囚の真ん中で十字架に架けられました。神のみ子が、罪人の中でも最たる者としての死を死んでくださいました。この真ん中という位置は、主イエスの頭上に掲げられた罪状書きをも目立たせることになったでしょう。
ヨハネによる福音書は、罪状書きのことを他の福音書以上に伝えます。都の外ではあるものの都近くにある刑場は、多くの人の目に触れ、多くのユダヤ人が罪状書きを読みました。主イエスのお働きにこれまで関心を寄せてきた人、主が都に入られた時歓呼して迎えた人、神殿の境内で語る主イエスの話しに耳を傾けた人、指導者たちから敵視されながら逃げもせず神殿で語る主イエスがどうなるのか好奇心で注目していた人、それぞれがどのような罪状で死刑に処せられたのか知りたがり、十字架に近付いてピラトが書かせた罪状書きを読んだことでしょう。
ピラトは罪状書きをヘブライ語、ラテン語、ギリシア語で「ナザレのイエス、ユダヤ人の王」と書かせました。この者はユダヤ人の王になろうと政治的な革命を試みた政治犯だと、示そうとしたのでしょう。それは結果として、主イエスがどなたであるのか世界に向けて示すものとなりました。この地域のユダヤの民が用いたヘブライ語、ローマ帝国の行政で用いられていたラテン語、この時代の世界言語であったギリシア語で記された罪状書きを見た、エルサレムの都を行き来するあらゆる地域出身の人々に対して、言い換えるならば世界中の人々に対して、主イエスが王であることを告げることになったのです。
この罪状書きに反発したユダヤの指導者たちは、「ユダヤ人の王」ではなく「ユダヤ人の王と自称した」と書き直して欲しいとピラトに、おそらく繰り返し、要請します。“これではこの者がユダヤ人の王であるかのようです。自分たちはそのようなことを認めていません”と。この要求をピラトは退けます。ピラトは、主イエスを有罪にする理由が無いと主張していたものの、ここまでユダヤの指導者たちに押し切られてきて、結局死刑に処することになってしまいました。罪状書きの書き直しを退けるのはピラトの最後の意地であり、ローマ帝国の総督である自分の方が彼らよりも上に立つ者であることを知らしめたかったのかもしれません。互いに自分の保身のために相手の力を利用し、上手く立ち回り、そうやって自分の世界で自分が王であり続けるために罪状書きを巡って紛糾し、このことに関してはピラトが主張を通しました。しかし罪状書きは、真の王はピラトでもユダヤの指導者たちでもなく、主イエスであることを告げています。捕らえられ、自由も弟子の大半も聴衆も失い、持っているものもほとんど失い、犯罪者として名誉も命までも失いつつあるこの方が、全ての民の王であるのです。
このような王を、誰が望むでしょうか。ピラトが思っているような政治的な王を望む人は多いでしょう。ユダヤの民の中にも、多くいたことでしょう。願いを実現してくれる王を、誰もが望む者であります。かつて主イエスが5つのパンと2匹の魚で大勢の群集の空腹を満たされた時、そのしるしを見た人々は主イエスを王に担ぎ上げるために連れて行こうとしました。人々がしようとしていることを知った主イエスは、そこを一人退かれました(6:15)。主イエスが望まれるなら、人々が期待する以上の王になることだって可能でした。主イエスが人々を罪から救うことを何とか阻みたいサタンは、主イエスがお働きを始める前に荒れ野で主イエスを、王にならないかと誘惑します。主イエスを非常に高い山に連れて行き、世の全ての国々とその栄華を見せて、これを全部与えると、ただし自分を拝むならば、と。その誘惑を主イエスは、ただ神さまだけを拝み、ただ主に仕えるのだと、旧約聖書の言葉を用いて退けられました。神さまに背を向ける思いがどれだけ人を惹きつけ、主義主張を超えて人を一つにしてしまうのか、私たちも多くの実例を知る者であります。主イエスが王であられる神さまの国は、神さまに背く力で人を支配するような王国ではなく、人々が期待するような地上の王国でもありません。「お前はユダヤ人の王なのか」「お前は王なのか」と尋問するピラトに、主イエスは、「私の国は、この世のものではない」と繰り返されました。主イエスは、世の力にも人の期待にも、サタンの力にも属さない、神様の国を地上に打ち立てるために、世に来られ、死んでゆかれるのです。
この福音書は、十字架の足元の二つの集団のことも伝えます。一つはローマの兵士たちです。主イエスから奪った服を、分け合っています。処刑される者の所有物は、刑を執行する者たちの取り分となったようです。主イエスの目の前で、もはや死んだも同然のお前には必要無いだろうと言わんばかりに山分けしています。それは詩編22:19の言葉が実現するためであったと福音書は伝えます。この詩編の詩人は、神さまに依り頼むその信仰故に、嘲りと罵声を浴びました。お前が信じる神など現実には無力なのだと、世の力こそが現実の王なのだと、獲物を狙う野獣のように詩人を取り囲み、逃げ場を奪われた詩人は、死の淵で苦しみ嘆きました。この詩編が伝える絶望の中に、主はおられます。僅かな持ち物も、身に着けていた衣も、肉体の力も奪われ、命までも奪われつつあります。雄牛や獅子や犬が牙を獲物に食い込ませるように、人々は主イエスの体に釘を打ち込みます。人の罪が幾重にも取り囲むただ中で、主イエスはその者たちを救うために苦しんでくださっています。
兵士たちが衣を四つに分けていることから、彼らは4人であったと考えることができます。もう一つの集団も4人と考えられます。主イエスの母マリアを含む3人の女性と、「愛する弟子」と呼ばれる弟子です。人数は同じでも、二つのグループは対照的です。片や主イエスを罪人、敗北者、死者と見なし、主のものを奪い、裂いてバラバラにする者たち、片や主イエスによって一つとされる者たちです。母と愛弟子に向かって告げられた主の言葉は、この福音書では十字架上で初めて主イエスが発せられた言葉であり、人に対して語りかけられた唯一の言葉となります。主イエス誕生の前からその救いを求めていたマリアと、主が去られた後も他の弟子たちよりも長く生きる者とされた愛弟子です。愛弟子はペトロに先んじて墓が空であることを知り、ガリラヤ湖でペトロに先んじて復活の主を認め、主イエスの十字架と復活を後代の人々に証しした人でもあります。古い世代と新しい世代の二人が、主イエスによって一つの家族とされます。ここで言及されているマグダラのマリアは、復活の主に空の墓の傍でお会いする者です。親子とされた2人を中心に、十字架の主を仰ぎ見、その死と復活の証人となった一人一人が主イエスによって結び付けられます。多くの人がここに教会の姿を見てきました。バラバラであった私たちは、主によってこのように神の家族と、一つの教会とされたのだと。王には見えないような王が、誰もそのような死を願わない最悪の死によって、一人一人を罪の力の奥底から救い出し、ご自分によって一人一人を結びつけてくださり、私たちを救う神さまの御業を成し遂げてくださったのです。
旧約聖書を引用しながら、神さまのご意志がみ子の苦しみと死に貫かれていたことをこの福音書は証しします。詩編22編はその終わり部分で、苦しみの中から嘆き叫ぶ詩人の祈りに、神さまが応えてくださったことを語り、信仰のきょうだいたちと共に神さまを褒め称えます。預言者イザヤが伝えた僕と呼ばれるものの姿もここに重なります。イザヤは53章で、正視するに堪えないような僕の苦しみを語ります。麗しさも輝きも、人々が憧れるようなものが何も無い者だとイスラエルの民は言い、軽蔑し、見捨て、あんなに苦しむのはごめんだと、あんなに神さまから遠い所に追いやられてしまう者にはなりたくないと言います。しかし、自分たちのこれまでと僕の苦しみを、新たな光の下で見る時がきます。主の羊であることを忘れてしまっていた自分たちを救うために、主なる神が自分たちの罪をすべて僕に負わせられたのだと。僕が担った苦しみは、自分たちが負うはずの病であり、自分たちが味わうはずの痛みであったのだと。僕は自分たちを義とし、自分たちの過ちと罪を背負い、命を死に至るまで注ぎ出して背く者のために執り成しをしたのだと。神さまが僕に、弱いこの自分たちを、与えてくださったのだと。
イスラエルの民が受けたのと同じような衝撃を、私たちも幾度となく受けます。この方が私の救い主なのだ、この方の痛みと苦しみと死は、敗北ではなく、罪による悲惨さの奥底から私たちを救い出し、ご自分の元へと招き、ご自分によって一人一人を結び付けるために、自ら負ってくださった私たちの罪の重さなのだと。正視するに堪えないキリストの苦しみと死を担ってくださった方こそ、私たちの王なのだと。